みなさんこんにちは。愛大研ハイスクール編集部です。
- 名古屋大学合格のため参考書選びに迷っている
- 今の実力からの名大合格に向けたレベル別の参考書ルートを知りたい
- 名大入試まで時間が限られているので、良い参考書を使ってなるべく効率的に勉強したい
今回はそんな悩みを持つ受験生に向けて、名古屋大学合格のための参考書ルートを科目別に解説します。
名古屋大学の志望学部が決まっている受験生にとっては、共通テスト対策を含めてどの科目から優先的に取り組むべきかも分かるように作成しました。
※本記事は、E判定からの逆転合格がコンセプトの「愛大研ハイスクール」の塾講師が、最新情報をもとに執筆しました。
はじめに|名古屋大学合格のために必要なこと
 画像:名古屋大学HP
画像:名古屋大学HP
名古屋大学は、研究力・学業の難易度・地元での人気という3つの軸で高い評価を誇る、「旧帝大」の名に恥じない総合力のある大学です。特に理系の研究環境は全国トップクラスで、自由で自主的な学びを求める学生にとって魅力的な選択肢となっています。
そんな名古屋大学に合格するべく本記事では、
-
名古屋大学の共通テスト・個別試験の配点と仕組み
-
各科目の勉強法(戦略的アプローチ)
-
レベル別参考書ルート(基礎・標準・合格)
を順に解説し、名古屋大学合格のために参考書ルートを構築し具体的な学習の道筋を提示します。
名古屋大学の入試制度|共通テストと個別試験の配点・特徴

名古屋大学の入試では、学部によって共通テストと二次試験(個別試験)の配点比率が異なります。
まずは、その学習計画を立てるために名古屋大学の入試形式と科目ごとの配点を確認しましょう。
名古屋大学の一般入試は大きく「共通テスト」と「個別試験」の二段階で実施されています。ここでは「共通テスト」と「個別試験(2次試験)」の2つに分けて説明して行きます。
共通テスト
まずは名古屋大学の最新版の共通テストの科目別の配点を確認しましょう。
自分の行きたい学部・学科の共通テストの配点をしっかりここで押さえておきましょう。
参照:名古屋大学「入試情報」
※前期試験のみ掲載
文学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 |
教育学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間発達科学 | 950 | 200 | 200 | 200 | 100(200) | 200(100) | 50 |
※理科・地歴公民から3科目
法学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律・政治 | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 |
経済学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 |
理学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | 900 | 250 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 |
情報学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 950 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
工学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 635 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 35 |
農学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 950 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
医学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 950 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
共通テスト配点のポイント
名古屋大学の共通テスト配点は、多くの学部で共通テストの傾斜配点はほとんどなく950点満点が多いです。特徴的な学部を挙げると、
- 法学部:共テ配点は950点だが、個別試験配点が600点と共テ重視の配点
- 工学部:共テ配点が635点(個別試験は1300点)となっており、国語以外全ての科目で配点が約半分になる
といったところでしょうか。
後述する個別試験との配点比率は、「共テ:個別試験=1:2」以上となることが多いですが、共通テストも全体の配点のうち大きな割合を占めるのでしっかりとした得点が必要です。
具体的にはどの学部を志望するにしても75~80%の得点率が必要となります。
個別試験(二次試験)
名古屋大学の一般入試では個別試験の比重が大きい傾向があります。
以下に、各学部ごとの個別試験の配点を記します。
※個別試験において科目が選択できるものについては一例を表に示しています。また備考欄にてどの科目から選択できるかを記してあります。
参照:名古屋大学「入試情報」
文学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 1200 | 400 | 200 | 400 | – | 200 | – |
教育学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間発達科学 | 1800 | 600 | 600 | 600 | – | – | – |
法学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 | 小論文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律・政治 | 600 | 200 | 200 | – | – | – | – | 200 |
経済学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 1500 | 500 | 500 | 500 | – | – | – |
理学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | 1500 | 300 | 600 | – | 600 | – | – |
情報学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然情報 | 1100 | 400 | 400 | – | 300 | – | – |
| 人間・社会情報 | 1100 | 700 | (400) | – | – | (400) | |
| コンピュータ科学 | 1300 | 300 | 500 | – | 500 | – | – |
※人間・社会情報:数学・地歴公民から選択
工学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 1300 | 300 | 500 | – | 500 | – | – |
農学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科共通 | 1550 | 400 | 400 | 150 | 600 | – | – |
医学部
| 学科 | 合計点 | 外国語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 1800 | 600 | 600 | – | 600 | – | – |
| 保健学科 | 1650 | 500 | 500 | 150 | 500 | – | – |
※医学科は面接、志望理由書あり
※保健学科(看護・放射線技術・検査技術・理学療法・作業療法)は共通
個別試験(二次試験)配点のポイント
どの学部も個別試験重視であることがわかります。特に数学は文系学部でも全ての学部で課されており、配点も大きいです。
良く言えば共通テストの失敗を二次で取り返す余地がある一方、二次試験でしっかりと得点ができないと厳しい戦いになります。
英語・数学・理科(文系は国語・社会)の記述力がカギとなると言えるでしょう。
個別試験でも共通テストと同様に、配点の大きい科目を安定して得点できるような勉強計画を立てる必要があります。
各科目の勉強法|個別試験( 二次試験)へのアプローチ
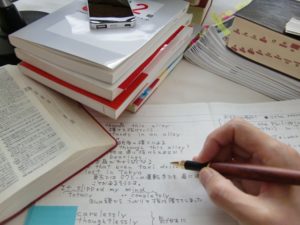
ここからは各科目でどのような力をつける必要があり、またどのような勉強法をする必要があるのかを解説していきます。
英語(文理共通)の出題傾向と頻出分野
ほぼ毎年以下の構成で出題されます:(105分・4題)
-
長文読解 ×2題(総語数:1,200 ~ 1,600語)
-
会話文読解 ×1題
-
自由英作文/和文英訳 ×1題
長文問題の傾向と対策
「論説文+専門的テーマ(心理学・環境科学・科学技術など)」が多く、人文・自然科学のバランスが良いです。書き取り・内容説明・空所補充・正誤問題など多様な設問形式を含みます。語数は合計1500語前後で、そこまで分量が多いわけではありません。語彙力で差がつく設問がかなり多く、近年要求される語彙レベルが高くなっています。長文問題に関しては圧倒的な語彙力で押し切るという勉強法が最も効果的だと言えます。単に語彙力といっても、単語帳の単語の意味が分かる、にとどまらず、その単語がどんな形でよく使われるのか、どんな語と相性が良いのかなど、必ずよく出る表現やコロケーションを意識して学習しましょう。コロケーションの知識だけで解答できる問題も多く、時間短縮にもなります。また英文の論理展開やディスコースマーカーの知識もよく問われます。
会話文問題の傾向と対策
内容一致の選択問題推定+末尾に 20~50語程度の意見英作文 が含まれることもあり、バランス重視といった出題傾向です。全大問の中で最も解き易いでしょう。長文問題と同様に語彙力を身につける勉強法が有効で、意見論述に関しては自由英作文の問題集を繰り返し解きましょう。
英作文問題の傾向と対策
2018年度から和文英訳問題から自由英作文問題に変わっています。これまでは図やグラフを読み取って記述するものが多かったのですが、2025年度は意見論述型が出題されました。このように出題形式は多岐に渡りますが、難易度としてはそこまで難しいものは出題されていません。標準レベルの問題集を手が勝手に動くようになるまで繰り返し解きましょう。その後、できるだけ多くの英文に触れて使える表現を増やしていきましょう。英作文では見たことのない表現は書かないが鉄則です。また書いた作文は必ず指導者や生成AIに添削を依頼しましょう。
数学(文系)の出題傾向と頻出分野
名古屋大学文系数学は大問3題・90分形式、理系との共通問題含む上、計算量や記述量も多く「理系レベル」の難易度が特徴です。傾向は以下の通りです。
標準~やや難の問題中心
-
オーソドックスな典型問題も出題されるが、難問も多いため完答が困難
-
普段の勉強では典型問題のインプットを徹底
微積・確率・数列が頻出
・特にこの3分野からの出題が頻出
・数列は難易度の高いものが多い
融合問題や数列に絡めた出題が多い
-
数列と他分野の融合問題が多く出題。特に確率漸化式が頻出
- 図形と方程式+微積分 もよく出題される
高い記述力と論証力が要求される
-
軌跡と領域や整数分野は、必要十分条件など正しく議論する必要がある
-
確率では複雑な場合分けをしなければならない問題が多い
- グラフを描いて議論する問題が多いため、正しいグラフを素早く描く必要がある
頻出単元
| 頻出分野 | 傾向の特徴 |
|---|---|
| 微分・積分 | 放物線接線、面積計算、増減表。頻出であり「標準的」で落としやすい部分 |
| 確率 | 近年は場合分けから確率を求める流れが多いが、確率漸化式など数列との融合問題も多く出題 |
| 数列 | 漸化式・和・数列の性質。図形や確率との組み合わせもあり |
| 図形・方程式 | 放物線・円や直線、領域と面積問題。微積と融合した問題も多い |
| 整数・ベクトル | 整数問題は出題頻度中程度。ベクトルは過去に登場ありだがやや希少(β) 。 |
※微積、確率、数列はほぼ毎年高頻度。整数・図形・ベクトルも出題あり
※確率漸化式は難問レベルだが頻出。2022年度以降減少が見られるが注意が必要
各分野の対策のポイントをまとめると以下のようになります。
-
頻出3分野(微積・確率・数列)を徹底演習
参考書で典型問題を一通りインプットした後過去10年分の共通&文系オリジナル問題で確実に得点できる力をつける -
記述・論証力の強化
小問の意図や誘導を読み取り、論理的に書く練習が必要。部分点狙いで複数の解法を考える訓練が効果的。必要十分条件などの論理を正しく学習することが必要。『数学の真髄』がおすすめ -
計算精度とスピード
理系と同等の処理力が必須。ミスを減らすために反復演習と復習が重要 -
応用問題への対応
特に確率漸化式や図形融合問題は応用力が求められる。『解法のセオリー』など演習教材で土台づくり -
過去問演習
特徴のある出題構成を把握し、時間配分・記述形式に慣れるため、10年分以上の過去問演習を推奨



コメント