みなさんこんにちは。愛大研ハイスクール編集部です。
- 立命館大学合格のため参考書選びに迷っている
- 高校3年間での勉強の順番が知りたい
- 立命館大学合格のための良い参考書を使ってなるべく効率的に勉強したい
今回はそんな悩みを持つ受験生に向けて、立命館大学合格のための参考書ルートを科目別に解説します。
関関同立の他大学との比較もしているので、まだ志望校が決められていない受験生も比較しやすいように作成しました。
※本記事は、E判定からの逆転合格がコンセプトの「愛大研ハイスクール」の塾講師が、最新情報をもとに執筆しました。
立命館大学の入試科目・配点
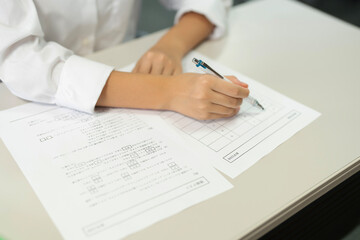
文学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
※国際文化学域、国際コミュニケーション学域の外国語の配点は150点です(合計350点)。
学部個別配点方式(文系)
| 配点 | 学域 | 英語 | 国語 | 選択科目(政治・経済/地理歴史/数学から1科目) | 合計 |
| 人間研究学域 | 100点 | 200点 | 100点 | 400点 | |
| 日本文学研究学域 | 100点 | 200点 | 100点 | ||
| 日本史研究学域 | 100点 | 100点 | 200点 | ||
| 東アジア研究学域 | 100点 | 200点 | 100点 | ||
| 国際文化学域 | 100点 | 100点 | 200点 | ||
| 地域研究学域 | 100点 | 100点 | 200点 | ||
| 国際コミュニケーション学域 | 200点 | 100点 | 100点 | ||
| 言語コミュニケーション学域 | 100点 | 200点 | 100点 |
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 70点 | |||
| 共通テスト | 国語 | 現代文のみ | 30点 | ||
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点 1科目 を採用 |
100点 | ||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』または 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
||||
後期分割方式(2科目型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
文学部はどの入試方式でも英語と国語の配点が大きくなっており、【英・国】重視の受験であることが分かります。また、学部個別方式では学域によって配点が変わるため、自分がどの科目を勉強すべきかを確認しましょう。
総合心理学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 70点 | |||
| 共通テスト | 国語 | 現代文のみ | 30点 | ||
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点 1科目 を採用 |
100点 | ||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』または 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1科目 |
||||
後期分割方式(2科目型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
総合心理学部も文学部同様、どの入試方式でも英語と国語の配点が大きくなっており、【英・国】重視の受験であることが分かるので、この2科目を重点的に勉強していきましょう。
産業社会学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地 理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計500点 | ||
| 国語 | 国語 | 150点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
200点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 国語 | 現代文のみ | 100点 | ||
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点 1科目 を採用 |
100点 | ||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
共通テスト併用方式(情報活用型・文系)
| 教科 | 教科 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | ||
| 共通テスト | 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
後期分割方式(2科目型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120 | 100 | 220 |
産業社会学部は入試方式によって教科の配点が大きく変わるため、自分が得意な教科の配点が大きい入試方式を選びましょう。
国際関係学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計350点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
※国際関係学専攻のみ受験可
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 150点 | 合計350点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点 1科目 を採用 |
100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
IR方式(英語資格利用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 英語 | 英語 | 100点 | 合計点300点 |
| 国際関係に関する英文読解 | 100点 | |||
| 英語外部資格試験(下記参照) | 100点 | |||
※英語資格点数換算表
| 換算点 | 英検 | TOEFL iBT | IELTS | GTEC | TEAP(4技能) |
| 100点 | 準1級または1級 | 72~120 | 5.5~9.0 | 1180~1400 | 309~400 |
| 90点 | ━ | 61~71 | 5.0 | 1100~1179 | 281~308 |
| 80点 | 2級 | ━ | 4.5 | 1050~1099 | 255~280 |
後期分割方式(2科目型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
国際関係学部はIR方式があり、自分が所持している資格、点数が何点に換算されるかを確認したうえで出願をしていきましょう。
政策科学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計350点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
150点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』または 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
後期分割方式(2教科型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計 |
| 配点 | 120 | 100 | 220 |
政策科学部はぬん学部と同様、英語と国語の配点が大きいため、【英・国】重視の入試であることが分かります。
法学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 | ||
| 国語 | 国語 | 150点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 国語 | 現代文のみ | 100点 | ||
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | ||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
後期分割方式(共通テスト併用3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ | ||||
法学部は他の学部とは学部個別方式と配点が変わるため、志望学部が決まっていない受験生は注意が必要です。
デザイン・アート学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(情報型理系)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 数学 | 情報 | 合計 |
| 配点 | 150点 | 150点 | 100点 | 400点 |
後期分割方式(英語、国語型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
デザイン・アート学部は2026年4月から新設される学部となっており、学部個別配点方式は情報が25%あるため、情報Ⅰの学習が必要になります。
経営学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 科目 | ||
| 外国語 | 英語 | ||
| 国語 | 国語 | ||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時にいずれか1科目を選択 |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||
| 日本史(日本史探究) | |||
| 世界史(世界史探究) | |||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、 数学B(数列)、数学C(ベクトル) |
||
※各学科の配点表
| 配点 | 学科 | 外国語 | 国語 | 選択科目 | 合計 |
| 国際経営学化 | 200点 | 100点 | 100点 | 400点 | |
| 経営学科 | 120点 | 100点 | 150点 | 370点 |
情報型文系(経営学科のみ)
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計370点 |
| 国語 | 国語 | 100点 | |
| 情報 | 情報(情報Ⅰ) | 150点 | |
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
情報活用型(文系)(経営学科のみ)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 |
| 国語 | 国語(現代文のみ) | 100点 | ||
| 共通テスト | 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
後期分割方式(2科目型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 合計点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
「経営学科で学ぶ感性+共通テスト」方式(経営学科のみ)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 「経営学部で 学ぶ感性」問題 (記述試験) |
発想力・構想力・ 文章表現力等を 通じ、「感性」を 評価します。 |
100点 | 合計700点 | |
| 共通テスト | 外国語 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目選択 | 高得点2科目を採用 | 200点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 2科目で400点(各200点) | |||
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」から高得点1科目 | ||||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」から高得点1科目 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」から高得点1科目 |
||||
| 情報 | 「情報Ⅰ」 | ||||
※共通テスト科目の得点率が65%(合計得点390点)以上であることが合格の必要条件です。本学独自試験(100点満点)の得点のみで合否を判定します。
学部個別配点方式では学科によって配点が変わるので、配点を確認して勉強すべき科目を確認しましょう。経営学部は入試方式によっては学科によって受験が出来ないものがあるので出願する際に確認しましょう。
経済学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(経済専攻のみ)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 数学 | 合計 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 150点 | 350点 |
共通テスト併用方式(5科目型)(経済専攻のみ)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点2科目を採用 | 2科目で100点(各科目50点) | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
共通テスト併用方式(6科目型)(国際専攻のみ)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」 | 50点 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 50点 | |||
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | 高得点2科目を採用 | 2科目で100点(各50点) | ||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
後期分割方式(共通テスト併用3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
経済学部は入試方式によっては受験できる学科が決まっているので、よく確認して勉強していきましょう。共通テスト併用方式(6科目型)は数学と情報が全体の25%を占めているので、他の学部よりも数学と情報の点数がより重要です。
食マネジメント学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
理系型3科目方式
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 数学 | (数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | 100点 | ||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時にいずれか1科目選択 | 150点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | (数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(情報文系型)
| 入試科目 | 外国語(英語) | 国語 | 情報 | 合計 |
| 配点 | 150点 | 100点 | 150点 | 400点 |
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
共通テスト併用方式(情報活用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | ||
| 共通テスト | 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
後期分割方式(共通テスト併用3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
| 情報 | 情報Ⅰ | ||||
食マネジメント学部は全学統一方式が文系メインの配点ですが、理系重視の入試方式もあるので理系の受験生も合格の可能性が大きくなっています。
理工学部
全学統一方式(理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 *物理科学科は「物理」必須 |
100点 | |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
学部個別配点方式(理科1科目型)
| 教科 | 科目 | |
| 外国語 | 英語 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
|
| 理科 | 物理、化学 | 解答時に選択 指定科目は学科により異なります。 |
※各学科の指定科目及び配点
| 学科 | 理科の指定科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 数学 | 理科 | 合計 | ||
| 数理科学科 | 「物理」「化学」から 1科目選択 |
100点 | 200点 | 100点 | 400点 |
| 物理科学科 | 「物理」必須 | 100点 | 100点 | 200点 | |
| 電気電子工学科 電子情報工学科 機械工学科 ロボティクス学科 |
「物理」必須 | 100点 | 150点 | 150点 | |
| 環境都市工学科 建築都市デザイン学科 |
「物理」「化学」から 1科目選択 |
100点 | 150点 | 150点 | |
学部個別配点方式(理科2科目型)
| 教科 | 科目 | |
| 外国語 | 英語 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
|
| 理科 | 物理、化学、生物 | 解答時に選択 指定科目は学科により異なります。 |
※各学科の指定科目及び配点
| 学科 | 理科の指定科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 数学 | 理科 | 合計 | ||
| 数理科学科 | 「物理」「化学」「生物」 から2科目選択 |
100点 | 150点 | 200点 | 450点 |
| 物理科学科 電気電子工学科 電子情報工学科 機械工学科 ロボティクス学科 |
「物理」「化学」 必須 |
||||
| 環境都市工学科 建築都市デザイン学科 |
「物理」必須、 「化学」「生物」から 1科目選択 |
||||
共通テスト併用方式(数学重視型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
| 共通テスト | 理科 | 「物理」「化学」から高得点1科目採用 *物理科学科は「物理」必須 | 100点 | |
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」および「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 100点 | ||
共通テスト併用方式(情報活用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
| 共通テスト | 理科 | 「物理」「化学」から高得点1科目採用 *物理科学科は「物理」必須 | 100点 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | ||
後期分割方式(理科、数学型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 *物理科学科は「物理」必須 |
100点 | 合計200点 |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)) | 100点 | ||
理工学部の全学統一方式と学部個別配点方式は、学科によって受験可能な理科科目が決まっている学科があるので、自分の志望学科や得意な教科によって勉強すべき科目を確認しましょう。
生命科学部
全学統一方式(理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
学部個別配点方式(理科1科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計350点 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
100点 | ||
| 理科 | 物理、化学 | 解答時にいずれか1科目選択 | 150点 | |
学部個別配点方式(理科2科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
100点 | ||
| 理科 | 物理、化学、生物 | 解答時に選択 指定科目は学科により異なります。 |
200点 | |
共通テスト併用方式(数学重視型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
| 共通テスト | 理科 | 「物理」「化学」から高得点1科目採用 | 100点 | |
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」および「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 100点 | ||
共通テスト併用方式(情報活用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
| 共通テスト | 理科 | 「物理」「化学」から高得点1科目採用 | 100点 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | ||
後期分割方式(理科、数学型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | 合計200点 |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)) | 100点 | ||
生命科学部は生物が受験で使えないため、生物履修者は化学で受験する必要があります。
情報理工学部
全学統一方式(理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 | ||
学部個別配点方式(理科1科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 | |
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
学部個別配点方式(情報型理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 | |
| 理科 | 情報Ⅰ | 100点 | |
共通テスト併用方式(数学、国語重視型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 200点 | |||
| 共通テスト | 国語 | 現代文のみ | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」および「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | ||||
共通テスト併用方式(情報活用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 |
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 200点 | ||
| 共通テスト | 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
後期分割方式(理科、数学型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | 合計200点 |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)) | 100点 | ||
情報理工学部は生物が選択科目として利用できるため、生物選択者も有利に戦うことが出来ます。また、【数・国】重視の入試方式もあるため、理科が苦手な受験生もチャレンジできます。
薬学部
薬学方式
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル) | 100点 | ||
全学統一方式(理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)) | 100点 | ||
学部個別配点方式(理科1科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計350点 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
100点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時に選択 | 150点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
学部個別配点方式(理科2科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計400点 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
100点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか2科目選択 | 200点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
後期分割方式(理科、数学型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | 合計200点 |
| 化学 | ||||
| 数学 | 数 学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)) | 100点 | ||
薬学方式は数学Ⅲ無しで受験ができるため、数学Ⅲが苦手な受験生でも薬学部を目指せます。また、学部個別配点方式ではどちらも理科科目重視の配点になっているので数学が少し苦手な受験生はこの入試方式が安全です。
映像学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計350点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
150点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
学部個別配点方式(理科1科目型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計350点 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B(数列)、 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) |
100点 | ||
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目を選択 | 150点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
学部個別配点方式(情報型理系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 |
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
共通テスト併用方式(情報活用型)
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | ||
| 共通テスト | 情報 | 情報Ⅰ | 100点 | |
後期分割方式(英語、国語型)
| 科目 | 英語 | 国語 | 配点 |
| 配点 | 120点 | 100点 | 220点 |
映像学部は全体的に入試方式が文系向けと理系向け両方があり、文理問わず受験することが出来ます。
スポーツ健康科学部
全学統一方式(文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |||
| 外国語 | 英語 | 120点 | 合計320点 | ||
| 国語 | 国語 | 100点 | |||
| 選択科目 | 公民 | 政治・経済 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 地理(地理総合、地理探究) | ||||
| 日本史(日本史探究) | |||||
| 世界史(世界史探究) | |||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | ||||
理系型3科目方式
| 教科 | 科目 | 配点 | ||
| 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 | |
| 理科 | 物理 | 解答時にいずれか1科目選択 | 100点 | |
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル)) | 150点 | ||
学部個別配点方式(文系型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 150点 | 合計400点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 150点 | |||
| 共通テスト | 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | 解答時に いずれか 1科目選択 |
100点 | |
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列)、数学C(ベクトル) | ||||
学部個別配点方式(情報型文系)
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 英語 | 100点 | 合計320点 |
| 国語 | 国語 | 100点 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 120点 | |
共通テスト併用方式(3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
後期分割方式(共通テスト併用3科目型)
| 教科 | 教科 | 配点 | |||
| 個別試験 | 外国語 | 英語 | 100点 | 合計300点 | |
| 国語 | 現代文のみ | 100点 | |||
| 共通テスト | 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 高得点1科目を採用 | 100点 | |
| 公民 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | ||||
| 地理歴史 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」 | ||||
| 理科 | 『「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から2出題範囲』 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
||||
| 情報 | 情報Ⅰ | ||||
スポーツ健康科学部は理系の受験生でも受験は可能ですが、学部個別配点方式の定員数を考慮すると、文系の入試方式で受験するほうが合格率は高いです。
立命館大学の出題傾向|入試難易度

立命館大学の難易度や入試傾向を確認しながら、自身の現在の学力を把握し、効果的な対策を立てていきましょう。
出題傾向
学部学科によって標準~難レベルまで様々です。
そのため、以下の出題傾向で各科目についての入試難易度を確認しておきましょう。また、頻繁に出題される分野がほとんどの科目で判明しているため、頻出分野から勉強を進めていきましょう。
| 科目 | 出題傾向 |
| 英語 | 文章のレベルは標準ですが、700語程度の長文を速読させる傾向にあるため総合的な難易度が少し高いです。 |
| 国語 | 文章のレベルは標準ですが、古文では学校の授業では扱わないような文章が出題され、出題方法も様々です。 |
| 文系数学 | 問題は標準レベルですが、計算力が求められる問題が近年増えてきているので注意が必要です。 |
| 理系数学 | 微分積分や複素数平面、整数の性質、確率が頻出分野です。また、文系数学と同様に計算力が求められる問題が多いです。 |
| 日本史 | 記述形式となっており、単語を漢字で正確に書ける必要があります。そのため、関関同立の中では難しいです。 |
| 世界史 | 日本史と同様記述ですが、問題のレベルは標準です。中国史が特に頻出になっています。時代的にはあまり偏りがなく古代から現代まで満遍なく出題されます。 |
| 政治経済 | 偏りは少なく、まんべんなく出題されます。しかし、1900年代の後半に関する政治・経済の事項はやや高い確率で出題されています。出題形式としては、用語を記述する問題が多いです。 |
| 地理 | 思考問題、論述問題が多いため、難易度が高くなっています。出題範囲に偏りはなく、全範囲から出題されます。 |
| 物理 | 力学と電磁気は毎年出題され、残りの分野から大問1題分出題されます。選択問題のみとなっています。 |
| 化学 | 有機化学の出題が50%を占め、25%が無機化学、25%が理論化学となっています。暗記と理解の両方が求められます。 |
| 生物 | 遺伝、体内環境、 動物の反応、細胞、代謝が頻出の分野となっており、ほとんど毎年出題されます。 |
受験科目を決める際に各科目の傾向を確認することで合格に近づくでしょう。また、志望する学部学科がすでに決まっている生徒は出題傾向を意識しながら勉強していきましょう。
入試難易度と偏差値
| 学部名 | 偏差値 |
| 文学部 | 52.5~60.0 |
| 総合心理学部 | 57.5~60.0 |
| 産業社会学部 | 52.5~55.0 |
| 国際関係学部 | 57.5~67.5 |
| 政策科学部 | 55.0~57.5 |
| 法学部 | 55.0 |
| 経営学部 | 57.5 |
| 経済学部 | 52.5~55.0 |
| 食マネジメント学部 | 52.5 |
| 理工学部 | 50.0~57.5 |
| 生命科学部 | 52.5~55.0 |
| 情報理工学部 | 57.5 |
| 薬学部 | 52.5~55.0 |
| 映像学部 | 52.5 |
| スポーツ健康科学部 | 52.5 |
文系学部は全体的に偏差値が55~60、理系学部は52.5~57.5となっており、学部により大きく変わりますが地方国立大学よりもやや高いです。西日本の私立大学の中では上位のレベルに位置しています。
次に、関関同立の他大学と比べた偏差値表を見てみましょう。
| 大学名 | 文系学部平均偏差値 |
| 同志社大学 | 58.7 |
| 立命館大学 | 54.6 |
| 関西学院大学 | 54.5 |
| 関西大学 | 54.2 |
関関同立の中での序列としては
同志社大学>立命館,関西学院大学>関西大学
となり、立命館大学は西日本では上位の大学と言えるでしょう。しかし学部によって偏差値にばらつきがあるので、学部がすでに決まっている際は大学選びが重要になります。
【科目別】立命館大学合格に向けた参考書ルート
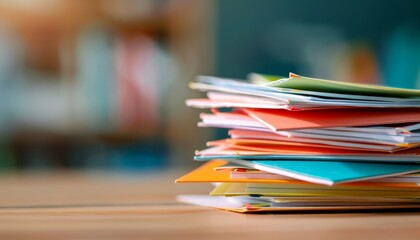
多くの受験生が悩む参考書選びですが、以下では各科目についてどのような参考書ルートで勉強を行っていけば良いかを確認していきましょう。
英語の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | ターゲット1900 | 入試必須の1900単語を押さえることが可能。共通テストや他大学の入試にも幅広く対応。これさえすれば英単語の不安はなくなる。 |
| 英文読解入門基本はここだ! | 英短文の問題が掲載されており、解説が細かくコンパクトです。これを終えると共通テストレベルの英文が読解可能。 | |
| 標準レベル | 全レベル問題集2,3 | 共通テストから標準私大レベルの問題を演習可能。少し長めの文章を演習可能。 |
| これだけはやっておきたい 英語長文500 | 標準~やや難レベルの英語長文を演習可能。解説が細かく、精読の練習も可能。 | |
| 合格レベル | 全レベル問題集4 | 私立上位レベルの英文の演習を行います。読解が中心のため、精読のスキルを身に付ける。 |
| これだけはやっておきたい 英語長文700 | 上位私立大~難関国立レベルを演習可能これが出来れば英語の心配はない。語数が立命館大学と同じなので繰り返し解いていく。 |
英語は奇問・難問が少ないですが、1つの長文で700語以上あるので速読力が求められます。勉強の際はストップウォッチを使って早く読む練習を心掛けましょう。
国語の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 古文単語帳 (学校で配布のものなど) | 入試必須の約300単語を押さえることが可能。共通テストや他大学の入試にも幅広く対応。市販のものと学校配布のものは大して変わらないことが多い。 |
| 現代文単語帳 (学校で配布のものなど) | 後回しにされやす現代文単語だが、知っておくと文章読解での解像度が飛躍的に上がる。市販のものと学校配布のものは大して変わらない。 | |
| 標準レベル | 富井の古文読解を 初めから丁寧に | 古文読解に不安がある生徒は訓練すべき一冊。 |
| 入試現代文へのアクセス (基本編) | 基礎空~標準レベルの文章を読解可能。解説がしっかりしているので、解説の読み込みに時間を割くべき。 | |
| 合格レベル | GMARCH&関関同立の古文 | GMARCH&関関同立の過去問が掲載されており、実践的な演習が可能。 |
| 立命館大学の赤本 | 最低6年分、できれば10年分を演習したい。出題形式に慣れていく。 |
記述問題が出題され、レベルとしては標準です。しかしながら、古文は教科書や参考書にあまり掲載されていない文章を用いることがあり、加えて設問も漢字の読み・文法・知識問題・文学史・和歌修辞技法・口語訳と非常に多方面から記述を含む形で出題されるので赤本演習を通して古文の傾向に慣れていきましょう。
文系数学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 白チャート | 教科書レベルの問題から入試基礎レベルの問題を演習していく。数学が苦手な人向け。 |
| 数学の入門問題精講 | 教科書を見てもわからない人はここから始める。 | |
| 標準レベル | 黄色チャート | 暗記必須な公式や、基本問題と典型問題の演習を積み、解法を覚えていく。 |
| 数学の基礎問題精講 | 数学の典型問題が豊富な問題集。記述能力を養っていく。 | |
| 合格レベル | 青チャート | 必要な典型問題から思考力を問う発展問題まで網羅されており、高得点を取るならここまでやっておきたい。 |
| 数学の標準問題精講 | 典型問題の量はチャートより少ないが、レベルの高い問題が多く収録されているため、効率よく勉強ができる。 |
近年、計算量の多い問題が増加してきたため、演習を重ねていくことで簡単に計算する方法を身に付けていきましょう。面倒臭がる生徒が多いですが、計算力を磨くには時間がかかるので日々の勉強から意識しましょう。
理系数学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 黄色チャート | 暗記必須な公式や、基本問題と典型問題の演習をつみ、解法を覚えていく。難易度はそこまで高くないので1年生の時から演習。 |
| 数学の基礎問題精講 | 数学の典型問題が豊富な問題集。記述能力を養っていく。 | |
| 標準レベル | 青チャート | 必要な典型問題から思考力を問う発展問題まで網羅されており、高得点を取るならここまでやっておく。 |
| 数学の標準問題精講 | 典型問題の量はチャートより少ないが、レベルの高い問題が多く収録されているため、効率よく勉強が可能。 | |
| 合格レベル | 数学の重要問題集 | 難易度の高い問題が多く、様々な観点から問題を解く能力を身に付ける。 |
| 立命館大学の赤本 | 同志社大学の問題は癖がある問題が多いため、必ず6年分は演習を行い、可能であれば10年分は演習をしたい。 |
微分積分や複素数平面、整数の性質、確率が頻出分野なのでこの分野の演習は可能な限り多く行いましょう。また、計算量が多いため計算を丁寧にすることや計算量を減らす計算方法を行っていきましょう。
日本史の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 東進ブックス 日本史B一問一答完全版 | 日本史の単語等の基礎知識を身に付けていく。 |
| 標準レベル | 石川の日本史B実況中継 | 基礎知識に追加で細かい知識を身に付けていく。 |
| 合格レベル | 金谷のなぜか流れがわかる本 | 時代の流れを掴むことで高得点を狙っていく。 |
立命館大学の日本史は記述式の問題になっており、関関同立の中でも難しいです。そのため、用語を正しく漢字で書けるようになっておく必要があります。1回1回の記述模試を大切にしていきましょう。
世界史の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 一問一答のターゲット4000 | 世界史の単語等の基礎知識を身に付けていく。 |
| 標準レベル | 中高6年間の世界史が 10時間でざっと学べる | 基礎知識の確認と正誤問題の対策を行っていく。 |
| 合格レベル | 金谷のなぜか流れがわかる本 | 時代の流れを掴むことで、高得点を狙っていき周りと差をつける。 |
| 立命館大学の赤本 | 時間配分や空欄補充問題に慣れるために最低6年分は演習する。 |
記述形式の問題が出題され、レベルとしては教科書レベルの問題が多いです。しかし、やや細かい内容も問われるので用語集をしっかり確認しておきましょう。
政治経済の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 蔭山の共通テスト政治・経済 | 基礎から丁寧に解説されており、政治経済が苦手な生徒にも適している。 |
| 政治・経済一問一答 【完全版】2nd edition | 蔭山の共通テスト政治・経済を読むのと並行してこの問題集で単語を暗記していく。8割は最低でも暗記しておきたい。 | |
| 標準レベル | 畠山のスパっとわかる 政治・経済爽快講義 | 時事問題や統計解釈問題等の解法を詳しく解説しているため、他の問題集と並行して利用していきたい。 |
| 合格レベル | 実力をつける政治・経済80題 | 単語の暗記が終われば積極的に利用していく。できるまで繰り返し行い、受験までに最低でも5周はしておきたい。 |
| 畠山のスパっととける 政治・経済爽快問題集 | 『畠山のスパっとわかる政治・経済爽快講義』の問題集。多様な問題に対応できるようにして周りと差をつける。 |
立命館大学の政治経済は出題に偏りがなく、まんべんなく学習する必要があります。文章での記述問題はありません。レベルとしては標準のため、正しい学習ができていれば合格点を採れるでしょう。
地理の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | 学校で配布された 統計データ | 学校で配布されている生徒が多いですが、受験で重要な種々のデータを暗記して基礎知識を蓄える。 |
| 地図帳 | 国の位置、主要な緯度・経度を暗記して基礎知識を蓄える。 | |
| 標準レベル | 実力をつける地理100題 | 勉強したことを適切にアウトプットするために問題演習を繰り返し行っていく。 |
| 合格レベル | 立命館大学の赤本 | 難しい問題が多いため問題のレベルに慣れ、時間配分を考えて自分に合った方法を覚える。 |
立命館大学地理の難易度は高めです。細かな知識が求められる問題が多く、数字に関する問題が多いです。国ごとの人口など統計を細かく読まないと知らない情報も聞かれるので、統計を読みこみましょう。
物理の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | セミナー/センサー | 学校で配布されている生徒が多いですが、下記の問題集への土台になるため、8割できるようにしておきたい。 |
| 標準レベル | 物理のエッセンス | 物理の基本的な考え方を身に付けることが出来るが、何周も演習する必要があるので早くから取り組みたい。 |
| 合格レベル | 良問の風 | 典型問題が多く掲載されており、典型問題への不安がある生徒は何周もしておくべき問題集。 |
力学と電磁気は毎年出題されており、残りの波動、熱力学、原子から1題出題されています。レベルとしては標準的で、記述の問題(数式や数値のみ解答)が少しあるため、計算ミスをしないように問題集を周回ましょう。
化学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | セミナー/センサー | 学校で配られた人も多いはず。セミナーやセンサーを通して基本的な計算や暗記を行う。基本問題はすべて解けるようにする。 |
| 鎌田/福間の〇〇化学の講義シリーズ | 学校の教科書では書かれてない内容が少しあるが丁寧に解説されており、難関大レベルにも対応した参考書。 | |
| 標準レベル | 化学の基礎問題精講 | 典型問題からやや難の問題があり、重要問題集までは手が伸びない人におすすめ。 |
| 合格レベル | 化学の重要問題集 | ほぼすべての化学の問題が掲載されており、これを演習すれば十分。最初はほとんど解けないかもしれないが、それでも解法を覚えるまで繰り返し演習していく。 |
| 立命館大学の赤本 | 立命館大学は難問は少ないが、共通テストとは内容が異なるので最低6年分は演習。 |
立命館大学の化学は難問が少なく、有機化学の出題が多いです。特に有機化学は構造決定の問題も出題されるので、重要問題集の演習を繰り返し行っていきましょう。また、化学基礎が大問0.5個分出題されるので、高校1年生の時から対策可能となっています。
生物の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
| 基礎レベル | セミナー/センサー | 学校で配られた人も多いはず。セミナーやセンサーを通して基本的な計算や暗記を行い基本問題はすべて解けるようにする。 |
| 標準レベル | 生物の基礎問題精講 | 典型問題〜やや難の問題で構成されており、まずはこれを完璧にする。 |
| 大森徹の最強講座126講 | 実験に関する問題が多いため、繰り返し読み込むことで実験の内容や目的を暗記ではなく、理解していく。 | |
| 合格レベル | 立命館大学の赤本 | 標準レベルの問題が多いため、過去問演習を通して自信を付けていく。 |
立命館大学の生物はやや難しい問題も出題されますが、合格が決まるのは標準的な問題でどれだけ失点しないかです。記述問題が多く、20~30語で回答する論述の問題があります。出題範囲はほぼ全ての範囲から偏りなく出題されているのでバランスよく勉強すべきです。
各科目の勉強法|個別試験へのアプローチ

ここでは参考書ルートを参考にしながらどのようにアプローチしていくかを確認していきましょう。
英語
立命館大学の英語は以下の大問5題構成になっています。全体的に難問・奇問は少ないく標準的なレベルと言えます。しかし制限時間が80分と短く、大問1題にかけられる時間が短いためある程度の速読力が必要になってきます。
- 大問Ⅰ 長文読解
- 大問Ⅱ 長文読解
- 大問Ⅲ 会話文
- 大問Ⅳ 文法
- 大問Ⅴ 語彙
大問Ⅰ・Ⅱ長文読解
大問Ⅰ・Ⅱの長文読解は600~700語の問題文が頻出しており、内容のレベルは標準的ですが抽象的なものが多く、精読の能力が求められます。また、試験時間が短いため1題を20~25分で解く必要があり、速読の能力も求められます。
大問Ⅲ 会話文
大問Ⅲは難易度がそれほど高くないため、対策の優先順位としてはそれほど高くありませんが、英語で点数を稼ぎたい受験生は会話文特有の文法等に着目しながら対策していく必要があります。
大問Ⅳ 文法
文法問題は難易度が高いため、しっかりと対策していく必要があります。解く際は各問が何の単元の問題を出題しているのかを考えながら解くことがお勧めです。
大問Ⅴ 語彙
語彙問題は覚えているか、推測できるかの問題です。難易度は標準的なので参考書ルートの『ターゲット1900』を覚えることでほとんど解けるようになります。
英語の勉強法
勉強法としては参考書ルートの『ターゲット1900』の1~1500を7割ほど覚えるまで周回するのと並行して『英文読解入門基本はここだ!』を行います。これは高3の4月までには達成しておきたいです。その後『全レベル問題集2,3』が7~8割解けるようになるまでひたすら行い、『これだけはやっておきたい 英語長文500』を高3の9月までに終わらせます。この時点で立命館大学レベルの英文は問題なく読めるようになりますが問題形式や時間配分に慣れるため、立命館大学の赤本を最低6年分解き進めます。
国語
立命館大学の国語の出題構成は以下の様になります。現代文、古文両方とも設問が多岐にわたるため全体的に他の関関同立と比べて難しいです。また、学部や入試方式によっては現代文のみの入試であったり、古文ではなく漢文を利用した受験になるので注意が必要です。
- 現代文・評論
- 現代文・随筆
- 古文
現代文はジャンルが様々ですが、古文は平安時代の文章が多く、かつ、学校ではなかなか扱わない文章が多いので対策していく必要があります。
現代文
現代文の設問の種類としては、漢字書き取り、熟語・ことわざ、傍線部問題、脱文挿入、言い換え指摘・抜き出し、内容一致(不一致)問題、文学史関連など多岐にわたります。漢字と四字熟語は頻出のため、早い時期から一定の時間を割いて学習していきましょう。
古文
単語の意味、文法、傍線部現代語訳、内容一致問題、文学関連問題などが主な設問構成となっています。前書きの内容補助説明がなく、注釈はあるもののあまり頻出とはいえない出典のものが多いです。設問には難問も含まれていますが、古文の配点が大きいため、持っている知識を駆使して1問でも多く解きたいです。
国語の対策
現代文単語帳、古文単語帳、漢字問題集は早くから学校で配布されていることが多いため、高1のころから取り組みます。高2からは参考書ルートの『入試現代文へのアクセス』を使って、基本的な現代文の読解・記述を行っていきます。古文は助詞・助動詞の活用や文法を完璧にしてから読解に移ると効率が高くなるので『富井の古文読解を初めから丁寧に』を高2の夏ごろから行います。高3になってからは、現代文は『立命館大学の赤本』を行い、時間配分や幅広い出題形式に慣れていきましょう。古文は『GMARCH&関関同立の古文』を演習して本番と同レベルの問題を解いていきましょう。
文系数学
立命館大学の文系数学は以下のような大問構成になっています。
- 大問Ⅰ 空欄補充
- 大問Ⅱ 空欄補充
- 大問Ⅲ 記述
微分積分、ベクトル、場合の数・確率が頻出となっており、各大問それぞれに癖があります。空欄補充問題は答えだけ書けばよいので簡単に見えますが、少し考える必要がある問題ばかりなので注意が必要です。記述の問題でも比較的解きやすい問題があるのであきらめず解くことが大事です。
大問Ⅰ 空欄補充
小問集合形式の問題で確率が頻出になっています。また、整数の問題は難しいものが多いため、解けるところをミスなく解くことが必要になってきます。
大問Ⅱ 空欄補充
大問Ⅱでは商品の売り上げ数と材料の関係、複利計算等の経営に関する問題が多くなっており、立命館大学独特の問題があります。複利計算はチャート式の問題集、商品の売り上げ数と材料の関係の問題は共通テストの過去問にそれぞれ掲載されているため、参考書ルートからは少し外れた対策が必要になります。
大問Ⅲ 記述
ここでは微分積分分野からの出題が多いため、対策しておきましょう。難易度としては共通テストレベルになりますが、必要な記述が含まれているかが得点に影響してくるため、塾や学校の先生の添削を受ける必要があります。
文系数学の対策
文系数学の対策は、通常は『黄色チャート』もしくは『基礎問題精講』から行いましょう。しかし、数学がとても苦手な生徒は『白チャート』、『入門問題精講』、学校で配布されたものが『Focus Gold』の受験生の場合は、それでも大丈夫です。
高1からは授業で習った分野を『黄色チャート』で追いかけるように勉強していきましょう。高2でも黄色チャートを解くのですが、高2からは記述もできるようになっていきたいので、試験本番同様の記述形式で問題を解いていきます。高3ではすでにすべての分野を学習しているのでひたすら復習に入ります。高3の7月までに全体の9割の問題が解けるように黄色チャートの問題を演習していきます。8月は立命館大学の過去問を解き、弱点を探すとともに、時間配分や記述の仕方を覚えていきます。その後は『青チャート』または『標準問題精講』を解き、1ランク上の問題を演習していきます。12~1月ごろは、共通テスト演習する受験生も多いため、その際に大問Ⅱの演習を行いましょう。
理系数学
立命館大学の理系数学の問題構成は以下のようになっています。出題傾向としてはまんべんなく出題されますが、数Ⅲの微分積分、複素数平面、場合の数・確率が頻出です。
- 大問Ⅰ 空所補充
- 大問Ⅱ 空所補充
- 大問Ⅲ 空所補充
- 大問Ⅳ 空所補充
問題の難易度が安定しづらいため、合格ラインが毎年のように大きく変わりますが大体60%取れれば安全です。記述の問題がないため部分点がなく、1問のミスが合否に大きく影響します。
大問Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 空所補充
どの大問で何の分野が出題されるかは毎年変わるため、試験本番の最初に全問を確認する必要があります。直近3年のデータでは数Ⅲの微分積分が毎年出題されているため、今年度も出題されると予想されます。少し考えないといけない問題もあるため、日々の勉強の1問1問を時間をかけて解いていきましょう。
理系数学の対策
数学が苦手な人や、基礎力を強化したい人は『黄色チャート』から、数学を得点源にしたい人や、すでに黄色チャートをほとんど終わらせている人は『青チャート』がお勧めです。高校3年生の7月までには数学ⅠAⅡBCを7割解けるようにしておきましょう。特に、ⅠAは数学Ⅲに時間が割かれてしまい8月以降は手が回りづらいので、8割解けるようになっておきましょう。
高3の8月は立命館大学の赤本を解くこともあり、数学Ⅲに時間をかけていきます。また、この時に自分の苦手な分野や忘れている問題を洗い出し、9月以降は青チャートの問題の復習をメインに行っていきます。数学Ⅲは10月まで授業をする高校がほとんどですが、試験まで時間がさほどないため1週間で合計15時間は数学Ⅲにあてます。その後は青チャートを終えた後は『数学の重要問題集』をB問題(発展問題)まで行っていけば対策が出来ます。
日本史
立命館大学の日本史は以下のような出題構成になっています。
- 大問1 原始・古代
- 大問2 中世・近世
- 大問3 近代・現代
設問の中には細かい暗記を求められる問題もあるため、立命館大学の日本史はやや難です。また、1つの時代からよりもさまざまな時代から出題されます。
大問Ⅰ 原始・古代
原始・古代は出来事や人物の繋がりが薄く、そこそこ覚えにくい単語まで出題されるため暗記が難しいです。ですが、勉強法を工夫することで効率よく暗記が可能です。また、史料を基に答えていく問題が他の大問よりもやや多いです。
大問Ⅱ・Ⅲ
大問Ⅱ・Ⅲでは特別な対策が必要な問題名とはないため、一般の対策をすれば問題ないです。しかし、大問Ⅲのほうがやや問題数が多い為、時間配分に注意しましょう。
日本史の対策
まずは単語を暗記するところから始めていきましょう。高2から『東進東進ブックス 日本史B一問一答完全版』を繰り返し演習していきます。そして並行して『金谷のなぜか流れがわかる本』を使用していきます。時代の流れを掴むことでさらなる得点アップを狙っていきます。高3の7月までに2冊を8割ほどできれば理想です。また、8月に立命館大学の赤本を最低6年分解き、自分の苦手分野を確認していきます。それを踏まえて9月以降に総復習を行い、できていない問題1つ1つをつぶしていきます。また、更に高得点を目指したい受験生は『石川の日本史B実況中継』を利用して詳細な単語を暗記していきましょう。
世界史
立命館大学の世界史の出題構成は以下のようになっています。
- 大問Ⅰ 記述問題
- 大問Ⅱ 記述問題
- 大問Ⅲ 記述問題
- 大問Ⅳ 記述問題
全問記述形式になっており、語句記入や記号選択形式の問題が中心、論述はないです。大問2~3題はアジア史、大問1~2題欧米史が出題されるため、アジア史を少し意識して対策していきましょう。
大問Ⅰ 記述問題
大問Ⅰは中国前近代史の出題が多くなっています。設問としては詳細な知識を問われるのではなく、幅広い時代の流れの問題が多いです。しかし、近年は朝鮮、台湾、西・中央アジアなど境界地域の出題が多くなっています。漢字で答える問題が多いため、勉強する際は漢字のミスに気を付けましょう。
大問Ⅱ 記述問題
大問Ⅱでは大問Ⅰと同じくアジア圏の問題が多いです。頻出の出題内容としてはアヘン戦争~中華人民共和国になっていますが、朝鮮、台湾、西・中央アジアなどの境界地域が近年は大問Ⅰ同様出題が多くなっています。
大問Ⅲ・Ⅳ 記述問題
大問Ⅲはヨーロッパ(ギリシアローマ含む)の前近代、大問Ⅳは近現代史の時事問題に関係する内容がよく出題されます。最近はパレスチナやウクライナ、女性差別に関する問題等が出題される傾向があるため、近年の時事問題に注目しておきましょう。
世界史の対策
高2からは参考書ルートの『一問一答のターゲット4000』を行い必要な単語を暗記していきます。並行して『中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる』を使用してアウトプットを行っていきます。また、余裕があればさらに並行して『金谷のなぜか流れがわかる本』を使用して時代の流れを理解していきます。これを繰り返し行い、高3の7月までに8~9割分かるようになるのが理想です。8月に『立命館大学の赤本』を解き、時間配分や傾向を掴み、苦手な分野を知ります。そのうえで9月から苦手分野の対策、基礎・基本の総復習を行っていきます。
世界史は暗記メインなので、時間をかけるほど得点につながるのでとにかく量をこなしましょう。
政治・経済
立命館大学の政治経済は出題パターンが次の2通りです。選択問題もありますが、語句記入形式の問題が多いです。
- 政治2題+経済1題 計3題
- 政治1題+経済2題 計3題
出題範囲は幅広く、まんべんなく学習する必要があります。難易度としては標準なので一般的な対策をすれば問題ないです。また、試験問題が80分なのに対して問題数が比較的少ないため、時間にはやや余裕があります。
政治分野
立命館大学の政治経済はまんべんなく出題されますが、その中で出題頻度が多い分野としては日本の憲法(明治憲法、日本国憲法)がやや頻出、次いで国際政治(国連、冷戦、パレスチナ問題など)、近代民主政治という順になっています。
経済分野
経済分野の中で特に出題頻度が多い分野は国際経済(外国為替レート、国際収支など)と日本経済(高度経済成長、公害、農業、中小企業など)次いで市場メカニズム、金融、労働、社会保障となっています。
政治経済の対策
高2の間は学校の授業を追いかける形でよいので、参考書ルートの『蔭山の共通テスト政治・経済』を読み込みインプットを行い、並行して『政治・経済一問一答【完全版】2nd edition』でアウトプットを行って単語を覚えるようにしましょう。高3の7月までには8割の単語を暗記しましょう。8月は赤本演習を行い、苦手分野や自分の実力を確認していきます。また、さらに高得点を目指したい受験生は、高3に入ってから『実力をつける政治・経済80題』を解くことや、『畠山のスパっとわかる政治・経済爽快講義』&『畠山のスパっととける政治・経済爽快問題集』で詳細な知識を身に付けましょう。
地理
立命館大学の地理の出題構成は以下のようになっています。
- 大問Ⅰ 地理情報と地形図
- 大問Ⅱ 世界地誌
- 大問Ⅲ 系統地理分野
難易度は比較的高く、細かな知識まで問われます。特に数字に関する問題が多く、思考力が問われる問題も多いため、しっかりと対策していく必要があります。近年は論述の問題が増えてきているため、日々の勉強でなぜその答えになったのかを意識しながら勉強していきましょう。
大問Ⅰ
大問Ⅰは年にもよりますが、地理情報と地形図の問題が多いです。図を使った問題が多いため、共通テストの問題等で慣れておく必要があります。また、問題数が他の大問と比べて多いため、時間配分に注意が必要です。
大問Ⅱ
大問Ⅱは単語を記述する問題と思考力が問われる問題が多いです。単語記述の問題は問題数が多いため単語を意識した対策をしておきましょう。
大問Ⅲ
大問Ⅲは他の大問と比べて選択問題が多いですが、大問Ⅱ同様単語記述の問題も多いです。こちらの選択問題は知識問題というよりも思考問題よりなので、分からなくても考える事で答えを導き出すことが出来ます。
地理の対策
参考書ルートの『統計データ』と『地図帳』をメインに使っていきます。学校の授業で習った内容が何故そうなるのかに着目しながら学習していきます。授業で身に付けた知識を随時地図帳や統計データに書き込み、繰り返し見返すことで知識を身に付けていきます。高2の間は他の科目を優先させたいため、本格的な対策は高3から行います。
高3では、週に2~3日学習する程度で大丈夫です。高2のあいだにインプットした情報を基に『実力をつける地理100題』を演習を行います。この際に、正解・不正解に関わらず地図帳、統計データを確認して知識漏れがないかを確認していきます。
物理
立命館大学の物理の出題構成は以下のようになっています。全問記述問題ですが、数式や数値のみ記入する記述式とマーク式の半々となっています。
- 大問Ⅰ 空所補充問題
- 大問Ⅱ 空所補充問題
- 大問Ⅲ 空所補充問題
難易度としては標準ですが、計算問題が多く、1問にかけられる時間が短いため、計算力が求められます。
大問Ⅰ
大問Ⅰは毎年力学が出題されています。少し文章量が多いですが、ふたを開けてみればただの典型問題なのでしっかり基礎基本の問題を対策していきましょう。力学から網羅的に出題されます。
大問Ⅱ
大問Ⅱは電磁気が出題されやすいです。こちらも大問Ⅰ同様、分野全体から幅広く出題されるため、網羅的に勉強しておきましょう。
※力学と電磁気の出題順は逆になることがあります。
大問Ⅲ
大問Ⅲでは、波動、熱力学、原子から1題出題となります。どの分野が出題されるかはランダムなため、まんべんなく勉強しておきましょう。特に原子は手薄になりやすいため、周りと差が出来ないようにしっかり対策しておきましょう。
物理の対策
物理の対策としては、学校から配布された『セミナー/センサー』を学校の授業を追いかけるように演習していきます。8割できるように繰り返し演習していきます。しかし、学校の授業が分かりにくい生徒もいると思います。そういう生徒はセミナー/センサーをする前に『物理のエッセンス』を繰り返し行っていきましょう。その後、高3の7月までにセミナー/センサーを行います。『良問の風』に移り演習問題を解いて集中的に典型問題を演習していきましょう。また、8月は立命館大学の赤本を解いて自分の弱点の分野と問題を把握し、9月以降の演習で積極的に潰していきましょう。
化学
立命館大学の化学は以下のようになっています。難問は少なくなっており、難易度は標準的です。
- 大問Ⅰ 空所補充問題
- 大問Ⅱ 空所補充問題
- 大問Ⅲ 空所補充問題
- 大問Ⅳ 空所補充問題
出題分野は毎年若干変化しますが、平均して理論化学1題、無機化学1題、有機2題となっています。
理論化学
理論化学は大問Ⅰでよく出題されます。内容としては化学基礎の延長のような問題が頻出なため、高1のころから対策が可能です。しっかり暗記していく必要があります。
無機化学
無機化学は大問Ⅱで頻出です。特に知識問題が多いのが特徴です。しかし、計算問題も少なくないため、しっかり演習しておく必要があります。
有機化学
関関同立の中では珍しく、有機化学が2題出題されるのが特徴です。有機化学は範囲が幅広いですが、特に知識問題と構造決定の問題が目立ちます。また、高分子化合物の問題も多く手薄になりやすいため、しっかりと対策しておきましょう。
化学の対策
高1から化学基礎を取り組むことで、高2から始まる化学専門が深く身につくことができます。高2以降の主な対策としては、参考書ルートの『鎌田/福間の〇〇化学の講義シリーズ』を読みながら『セミナー/センサー』を演習し、8割解けるようにしましょう。その後、高3になってからは『基礎問題精講』を集中的に演習していき、7月までに8割解けるようにしましょう。その後、8月に立命館大学の赤本を解いて自分の苦手な分野と問題傾向を確認していきます。また、8月中から『化学の重要問題集』を解いていき、典型問題を繰り返し解いて定着させましょう。A問題が解けるようになれば立命館大学の化学の対策は完成です。
生物
立命館大学の生物は以下のような出題構成になっています。
- 大問Ⅰ 空欄補充、記述問題
- 大問Ⅱ 空欄補充
- 大問Ⅲ 空欄補充
- 大問Ⅳ 空欄補充
記述問題がメインになっています。しかし、近年は20~30字程度の論述も含まれるため、対策が必要です。また、遺伝,体内環境, 動物の反応,細胞, 代謝から頻出となっています。また、中にはやや難の問題が含まれます。
空欄補充問題
空欄補充問題では少し難問が入っていますが、そこでは合否は決まりません。得点できる問題を確実に取ることが重要ですが重要です。そのため、基礎基本の問題を繰り返し解いていきましょう。
記述問題
20~30字で解答する必要があり、論述する練習をしておきましょう。分かっていても文字数に収めることが難しいこともあるため、問題演習を通してしっかりと対策していきましょう。
生物の対策
高2から『センサー/セミナー』を繰り返し解き、単語を覚えていきましょう。高3までには学校の授業で習ったことを8割できるようになるのが理想です。高3の4月~7月は『基礎問題精講』を行いながら『大森徹の最強講座126講』を読み込み、特に実験の詳細をインプットとアウトプットしていきましょう。基礎問題精講は短い論述も含まれているため、対策かのうです。8月は立命館大学の赤本を演習して苦手な分野を確認していきましょう。最終的に基礎問題精講が6~7割解ければ対策としては完璧です。
立命館大学合格に向けた年間の受験生活
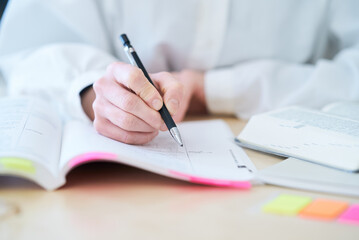
それでは、上記で紹介した参考書ルートを使って立命館大学に向けた3年間の受験生活を考えていきましょう。
高1まで
高校は最低でも偏差値60前後以上の高校に進学したいです。もし今通っている高校で十分な指導を受けることができていない場合は、塾や予備校に通うことをおすすめします。
また、高校受験を終えて春休みは十分に時間があると思います。その時間を使って、中学生の内容の復習と高校の内容の先取りを行っておきましょう。
高1~高2まで
高1~高2までの間は、勉強できる内容が限られています。数学、英語、国語、化学基礎は勉強ができるので、各参考書ルートを確認しながら演習していきます。
高1での偏差値の目安としては、模試で得意科目は55~60、苦手科目は50前後です。
高2から専門科目が始まります。また、数学は1年生の内容よりもさらに難しい分野を行うので、数学の勉強時間が少なくならないように時間の使い方に気を付けましょう。
高2での偏差値の目安は受験科目で得意科目は60以上、苦手科目は55です。
高3夏まで
参考書ルートに従って演習を行うことで、高3の夏までに基礎基本を押さえることが出来るので、高3の夏休みに個別試験対策として難易度の高い問題集を行うことが出来ます。
高3夏の偏差値の目安としては、受験科目で得意な科目は62.5、苦手科目は55~57.5です。
高3秋まで
夏に判明した苦手分野を、参考書ルートの問題集を使って徹底的に潰していきましょう。この時期は、ひたすら問題演習を行っていきます。参考書ルートの合格レべルを5割程度解けるようにするのが目標です。
この時期の偏差値の目安は目標とする学部学科の偏差値です。
高3冬
試験までの時間はひたすら問題演習を行いましょう。この時期は質よりも量が重要です。できなかった問題が解けるようになるまで繰り返し解いていきましょう。
立命館大学合格のための参考書ルートを作成しよう
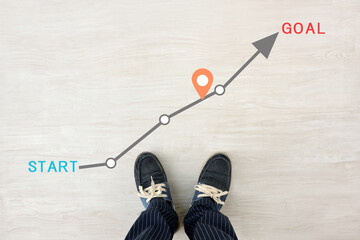
とはいえ、これらすべてを一人で完璧にこなすのは簡単なことではありません。第三者、特にプロ講師の力を借りることで、自分の現在地や目標との距離、そして今後やるべきことが明確になり、学習効率が大きく向上します。
プロによる対策や添削が非常に有効です。特に、二次試験を自分ひとりで採点・添削・対策を行うのが難しいため、専門的なサポートを受けることで大きな安心と実力アップにつながります
愛大研ハイスクールで立命館大学合格を目指そう

本記事を執筆した私の在籍する『愛大研ハイスクール 松山市駅前校』では現在、無料体験授業・個別相談会を受付中です。
愛大研ハイスクール紹介記事:【新ブランド開校】逆転合格専門塾「愛大研ハイスクール」松山市駅前に誕生!
愛大研ハイスクールでは、
- 講師は講師歴5年目以上のプロ講師 or 愛大医学部講師のみ
- 全授業完全1対1の個別指導のみ
- 自習コンサルティングで日々の学習を徹底管理
ハイレベルな受験指導を行っています。
授業の質・指導方針・学習戦略など、詳しく知りたい方は、ぜひ一度お越しください。
今のままで合格できるのか不安に感じている方は、面談だけでもお越しいただければと思います。
🔻無料体験・ご予約はこちら
📞 お電話:089-994-5105
💻 Webフォーム:https://aidaiken.com/trial/
📍所在地:松山市湊町5丁目(松山市駅徒歩2分)

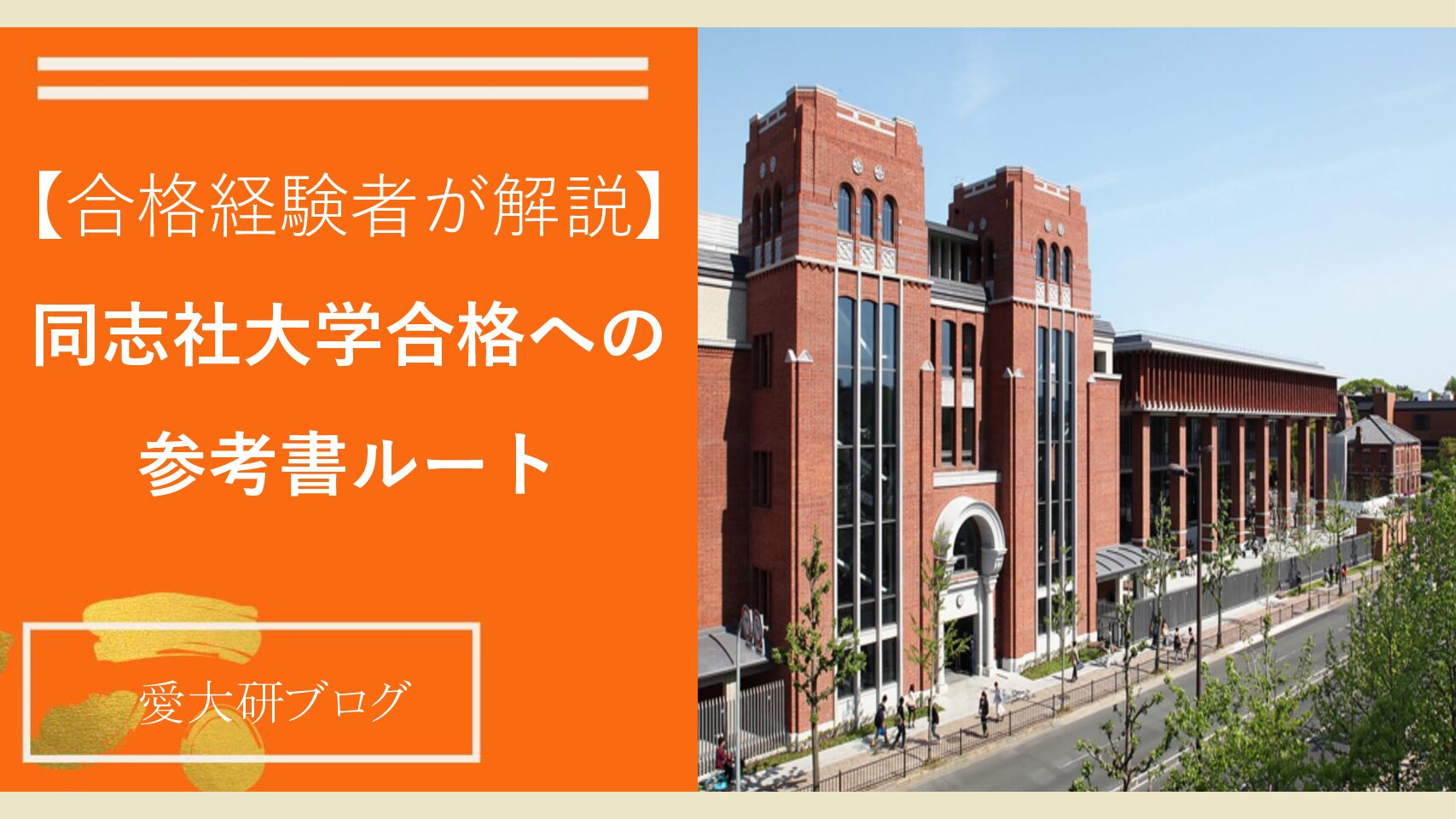

コメント