みなさんこんにちは。愛大研ハイスクール編集部の中村です。
今回は関西学院大学の入試傾向や、難易度・偏差値などを踏まえながら合格に向けた参考書ルートを科目別に詳しく解説していきたいと思います。
関西学院大学は同志社大学・関西大学・立命館大学などと並ぶ関西の難関私立大学で、毎年多くの受験生が志望します。そんな戦いに勝ち抜くためには、明確な戦略とそれを実行することが大切です。
また、関西学院大学は
●文系学部: 9学部 (文学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、人間福祉学部、国際学部、総合政策学部、教育学部)
●理系学部: 4学部 (理学部、工学部、生命環境学部、建築学部)
●その他:神学部
の以上14学部から構成された総合大学です。それぞれの学部において様々な入試方式があり、入試科目も違っています。今回は一般入試で受験をする方に向けて記事を書いていきたいと思います。
関西学院大学の出題傾向|入試難易度
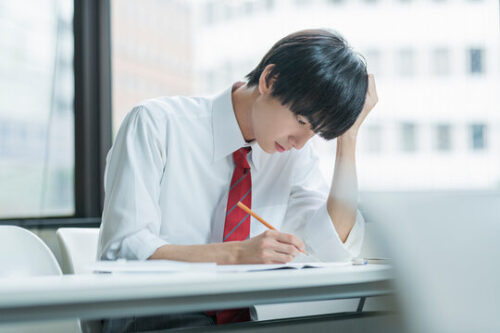
出題傾向
関西学院大学の各科目ごとの大まかな出題傾向は以下の通りです。
- 英語:難易度は標準~やや難レベルの総合力型で、長文重視の6題構成
- 国語:難易度は標準~やや難レベルで、論理的読解力と基礎知識が問われる構成
- 文系数学:標準レベル中心で計算重視・時間勝負の 3 大問構成(空所補充 ×2+記述式×1)
- 理系数学:標準レベル中心で構成され、計算力と記述力が問われる大問4題形式
- 日本史:幅広い知識を要し、正誤・史料・思考力重視の標準~やや難構成
- 世界史:基礎~標準レベルの全問マーク式で、正誤判定・語句選択中心の大問5題構成
- 地理:難易度は標準レベルの選択式で、大問5題構成
- 物理:大問3題構成で記述式で計算量は多めだが、難易度は基礎~標準レベル
- 化学:大問3題(理論・有機・無機融合)、記述問題を含み、難易度は基礎〜標準レベル
- 生物:大問3題構成。記述+実験考察重視で、難易度は標準〜やや高難度
入試難易度と偏差値
関西学院大学は、ほかの関西大学・同志社大学・立命館大学とあわせて関関同立とまとめられることが多く、受験生も関関同立の中からいくつかの大学を受験する人が多いので、今回は、この3つの大学と、関西学院大学について比較してみたいと思います。
まず偏差値についてですが文系の学部も理系の学部も、基本的に、同志社大学>立命館大学・関西学院大学>関西大学の順に偏差値が高いです。
立命館大学と関西学院大学に関しては学部によって偏差値の幅があり、理系の学部に関しては立命館大学のほうが偏差値が高い傾向があります。このように、関関同立の4大学の中で、関西学院大学は中間ほどの難易度であり、特に国際系の学部や経済系の学部に関しては関西学院大学のほうが立命館大学よりも偏差値が高くなっている傾向にあります。
関西学院大学の学部ごとの偏差値一覧は以下の通りです。
※入試方式や、学科によって同じ学部でも偏差値の幅があります。
| 学部 | 偏差値 |
| 国際学部 | 60.0~70.0 |
| 商学部 | 55.0~57.5 |
| 経済学部 | 55.0 |
| 法学部 | 52.5~57.5 |
| 社会学部 | 52.5~57.5 |
| 文学部 | 52.5~55.0 |
| 人間福祉学部 | 50.0~52.5 |
| 教育学部 | 50.0~55.0 |
| 総合政策学部 | 50.0~52.5 |
| 理学部 | 50.0~52.5 |
| 工学部 | 50.0~55.0 |
| 生命環境学部 | 50.0~52.5 |
| 建築学部 | 52.5 |
| 神学部 | 50.0 |
全体的に文系の学部のほうが理系の学部よりも偏差値が高くなっています。
また、入試方式別に見てみると、『共通テスト利用方式』や『共通テスト併用方式』のほうが、学科試験のみの一般入試よりも偏差値が高くなっています。
これは、同志社大学を第一志望とする受験生が、滑り止めとして関西学院大学を共通テスト利用方式で受験するケースが多いことが、その要因の一つと考えられます。
【科目別】関西学院大学合格に向けた参考書ルート

英語の参考書ルート
関西学院大学の英語試験は、すべての学部で同じ形式で行われます。
試験時間は90分、大問6題構成です。
日程に応じて若干異なりますが、出題の中心は長文読解・文法・語法・語句整序・会話文・英作文(個別日程では記述式を含む)であり、他の私立大学と大きく異なるユニークな特徴はありません。基本的にはオーソドックスな入試問題であるため、しっかりと基礎から標準レベルの英語力を地道に鍛える姿勢が合格への近道となります。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | ターゲット1900 |
この参考書は出現頻度順に単語が並んでいるため、重要度の高い語から優先的に学習でき、短期間で入試の土台を固められます。さらに、各単語には派生語や熟語が併記されており、関学の文法・語法問題や長文中の言い換え表現にも対応しやすくなります。また、全単語に例文がついているため、暗記だけでなく文脈の中で使える語彙として定着させることが可能です。この例文学習は、個別日程で出題される和文英訳や英作文の表現力向上にも直結します。 |
| 英文法ポラリス |
関西学院大学の英語入試では、長文読解に加えて文法・語法問題も毎年出題されます。特に空所補充や語句整序といった形式では、単なる暗記ではなく、文脈に沿った正しい文法運用力が求められます。『英文法ポラリス』は、この「理解して使える文法力」を養うのに適した参考書です。難易度に関しても適切であると思います。 |
|
| 関西学院大学合格レベル | やっておきたい英語長文300/500 |
関西学院大学の英語は、全体の配点の約6割を長文読解が占めており、1題あたり500〜800語程度の文章を素早く正確に読み解く力が必要です。『やっておきたい英語長文300/500』は、この長文読解力を段階的に養成するのに最適なシリーズです。 まず、『300』は1題あたりの語数が関学の短めの長文や部分読解に近く、精読力を鍛えるのに向いています。文構造や段落展開を丁寧に追いながら解く練習ができ、初期段階での読解基礎固めに役立ちます。次に『500』では、関学の標準的な長文と同程度の語数・難易度になり、本番に近い感覚で速読と内容把握を練習できます。 また、このシリーズは出題形式やテーマの幅が広く、設問タイプも関学に似ている点が強みです。内容一致、段落要旨、空所補充、言い換え問題など、関学頻出の設問形式に自然に慣れることができます。さらに、解説が詳細で、本文の重要表現や構文も丁寧に解説されているため、単に正解を確認するだけでなく語彙・文法・構文の総合復習が可能です。 |
国語の参考書ルート
関西学院大学の国語は、大問3題(現代文1・古文1・漢文または古文2)で、試験時間は80分です。
現代文は評論や随筆が中心で、古文は物語や日記文学に加え和歌がよく出題されます。
漢文は基本句形が中心ですが素早く正確に解く力が求められ、全体を通して精読力と選択肢の正確な判断力が鍵となってきます。
| 現代文 | ||
| 参考書 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | 現代文読解力の開発講座 | 関学の評論文は、抽象的なテーマが多く、段落ごとの論理的な関係を正確に追う必要があります。この本は「論理マップ」を使って、接続詞・指示語・要約の練習を徹底できるため、言い換え問題や根拠を探すような選択肢の対策に適していると思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 入試現代文へのアクセス 基本編・発展編 | 設問の形式が関西学院大学の過去問と近く、本文の難度も適切だと思います。特に選択肢の細かいニュアンスの違いを見抜く練習が多く、関西学院大学に特有の「部分的正答と全体正答を区別する問題」を練習できます。 |
| 古文 | ||
| 参考書 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | マドンナ古文単語230 | 関西学院大学は古文単語の難度がやや高く、文学的・和歌的な単語の意味を問うことが多いです。この単語帳は例文が現代語訳付きで、文章中で意味が思い出しやすくなるのが利点です。 |
| 関西学院大学合格レベル | 富井の古文読解をはじめからていねいに | 関西学院大学は古文の文法問題単体というよりも本文中での文法の解釈を問う傾向があります。この本は文法知識を文脈内で使う練習が豊富なので、「知識はあるけど本文では迷ってしまう」というような受験生に有効です。 |
| 漢文 | ||
| 参考書 | おすすめ理由 | |
| 関西学院大学合格レベル | 漢文早覚え速答法 | 関学の漢文は出題されない年もありますが、出題されると基本句形が多く、スピード勝負になります。この本は句形を短期間で習得でき、試験での実践力になるし量もそこまで多くないので出題される年に備えるための参考書として適していると思います。あとは赤本で演習をするのをおすすめします。 |
文系数学の参考書ルート
関西学院大学の文系数学は、大問3〜4題の構成で試験時間は60分です。
標準〜やや難レベルの典型問題が中心で、数列・確率・図形・微積が頻出します。基礎力と問題の処理能力が得点の鍵となるでしょう。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 基礎問題精講 | 教科書レベルから入試基礎へ移行できる構成で、関西学院大学の標準問題に直結します。丁寧な解説があるので独学でも理解しやすいと思います。また、網羅系参考書に比べて問題数も抑え目なので文系の人でも着手しやすいと思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 1対1対応の演習[ⅠAⅡB] | 少し難易度は高めですが、公式や定理の使い方を深く理解できる参考書です。解法の根拠を明確にでき、記述形式の練習にも有効だと思います。 |
| 関西学院大学 赤本 | 関西学院大学の受験において出題傾向や時間配分の練習は欠かせません。また、同じようなパターンが多いため、過去問演習は得点アップにも直結します。 |
理系数学の参考書ルート
関西学院大学の理系数学は、大問3〜4題の構成で、試験時間は90分です。
難易度は標準〜やや難レベルの問題が中心です。誘導付きで部分点を狙いやすいですが、計算量が多く時間配分が得点の鍵となってくると思います。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | Focus Gold 数学ⅠAⅡBⅢ | 網羅性が高く、入試の典型問題が広いレベル帯で揃っています。関西学院大学で頻出するテーマを体系的に整理でき、基礎固めになります。 |
| 関西学院大学合格レベル | 1対1対応の演習[ⅠAⅡBⅢ] | 文系数学と同じく理系数学もこの参考書で上記のような網羅系参考書でインプットした数学的な考え方をアウトプットする練習になると思います。 |
| 関西学院大学 赤本 | 私立大学は問題に特徴があり、それは関西学院大学の理系数学にも当てはまっているので出題形式や計算量、実践力を過去問で鍛えることはとても重要です。過去問分析で「捨て問」と「確実に取る問題」の選別が出来るようになることが好ましいです。 |
日本史の参考書ルート
関西学院大学の日本史は、大問4題前後・試験時間60分。全問マーク式です。
文化史・近現代史の出題比率が高く、史料や長文を使った問題も多いです。単語暗記だけでなく、時代の流れや分野間の関連性を押さえる必要があります。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | 日本史B講義の実況中継 | 語り口調の解説で、通史をストーリーとして頭に入れやすいのがおすすめポイントです。関西学院大学で頻出の文化史や近現代史も、登場人物や背景がイメージしやすくなり、記憶の定着がしやすいと思います。暗記とはいえ、理解を伴わせられると思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 日本史B 一問一答 | 全国の入試頻出の語句を網羅した定番の参考書です。短時間で回せる構成なので、スキマ時間で知識を積み重ねやすいと思います。関西学院大学の細かい用語問題は難しい漢字や人名、文化史用語が多く、この参考書で知識量を多くすることで失点を防げます。 |
| 関西学院大学 赤本 | 過去問演習を通じて、文化史や近現代史の出題頻度、史料問題のパターンが見えてきます。5〜7年分を分析すると、繰り返し出てくるテーマやひっかけ方が把握でき、無駄なく重点的な対策が可能になります。時間配分や解く順番のシミュレーションも重要です。 |
世界史の参考書ルート
関西学院大学の世界史は、大問4題前後・試験時間60分の、全問マーク式です。
図や地図、史料を用いた長文問題も多いです。単純に用語を暗記するだけではなく、時代の流れと地域間のつながり、背景知識を踏まえて解答する力が必要です。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | 世界史講義の実況中継 | 会話口調で初学の人でも分かりやすく、人物や文化史のイメージが記憶に残りやすいのがおすすめのポイントです。関西学院大学で頻出の文化史や美術史、思想史もストーリーとして覚えられ、暗記が苦手な人に特にオススメです。 |
| 関西学院大学合格レベル | 世界史B 一問一答 | 入試において頻出の用語を網羅した定番の参考書です。関西学院大学の世界史は文化史や人物名、年号も問われるため、正確な用語の暗記はとても重要です。この一冊を繰り返せば、基礎知識を漏れなく習得できると思います。また、アウトプットにも役立てられます。 |
| 関西学院大学 赤本 | 私立大学は問題に特徴があるので過去問演習で、時間配分の感覚を養ったりしていくのはとても重要です。また、文化史や近現代史の出題頻度やテーマ史の傾向を把握できます。関西学院大学合格に向けて効率的な学習を心がけたい人は、アウトプットで早いうちから赤本を利用することをおすすめします。 |
地理の参考書ルート
関西学院大学の地理は、大問4題前後の構成で試験時間は60分の、全問マーク式です。
統計や地図、写真などの資料問題の比率が高いため、単なる暗記ではなく、暗記した知識を活かすことで資料を読み取って推論する力と、統計やグラフの変化を説明できることが求められます。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | 村瀬のゼロから始める地理B | 初学の方や、地理に苦手意識のある受験生でも理解しやすいストーリー形式で、地理の流れや仕組みをイメージしながら学べます。受験の地理の基礎的な内容を一冊でカバーでき、関西学院大学の問題を解くための知識の土台を築くのに適していると思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 実力をつける地理100題 | 入試実戦レベルの良問がバランスよく出題されており、解説は正解の理由だけでなく背景知識や関連情報まで丁寧に説明してくれるため、問題演習を通して知識の補強と応用力の養成が同時に可能な1冊です。過去問だけでは不足しがちな演習量を補い、本番でのスピード感と判断力を磨けると思います。 |
| 関西学院大学 赤本 | 関西学院大学に特有の統計やグラフの種類や選択肢のパターンなどに対応するためには過去問演習が最も効果的です。5〜7年分を分析すると、解答の手順や時間配分が安定し、本番でのミスを大幅に減らすことができるので、インプットがある程度済めば早いうちから着手して大丈夫です。 |
物理の参考書ルート
関西学院大学の物理は、大問3〜4題の構成で試験時間60分の全問マーク式です。
力学・電磁気・波動・熱力学の4分野がバランスよく出題されます。誘導付きの問題構成が多いですが、途中で急にレベルが上がる設問もあり基礎の応用力が合否を分けます。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | セミナー物理 | 教科書と併用できるため網羅性が高く、例題と練習問題で基礎〜標準のレベルを固めることができ、初学者におすすめです。抜けやすい公式や条件整理を丁寧に確認できると思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 重要問題集 物理 | 頻出分野を網羅した定番の問題集で、計算演習量が多く、特に力学・電磁気の反復練習に向いています。解答パターンの定着と計算スピードの向上に効果的です。 |
| 関西学院大学 赤本 | 私立大学は問題が特徴的なので、過去問を5〜7年分演習することで、時間配分や誘導への対応力を上げることができ、本番での得点安定化につながります。また、過去問分析により、頻出パターンや苦手分野を理解しそこを再度固めることができ効率的です。 |
化学の参考書ルート
関西学院大学の化学は、大問3〜4題の構成で試験時間60分の全問マーク式です。
計算問題の比率が高く、化学平衡や電池の問題、熱化学などでは途中式の理解が必要です。有機は構造決定や反応経路、無機は性質や製法など暗記分野が多く、総合力が問われます。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | セミナー化学 | 網羅性が高く、例題と練習問題で基礎〜標準のレベルを幅広くカバーでき、基礎固めに適しています。教科書とも併用できるので、基礎知識の整理に適しており、特に無機化学の定着に有効だと思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 重要問題集 化学 | 入試頻出分野を網羅した定番の参考書です。関西学院大学レベルからするとオーバーワークな問題もありますが、全体的に化学の問題を網羅できますし、計算問題の演習量が豊富です。解説も詳しく、間違えた問題を徹底復習しやすい構成なのでおすすめです。 |
| 関西学院大学 赤本 | 関西学院大学に特有の問題傾向に対応するのには赤本の演習は欠かせません。5〜7年分を解くことで、頻出分野の見極めと時間配分の感覚を身につけられます。ある程度基礎が固まったと思う方から早めに着手していってください。 |
生物の参考書ルート
関西学院大学の生物は、大問4題前後の構成で、試験時間60分の全問マーク式です。
特徴として、図表や実験データを使った考察問題の比率が高い点が挙げられます。単純な知識の暗記だけでなく、グラフの読み取りや、与えられた条件から論理的に答えを導く力が求められます。
| 参考書名 | おすすめ理由 | |
| 基礎レベル | セミナー生物 | 教科書と併用ができ、網羅性が高く、基礎的な用語から標準的なレベルの知識まで幅広く確認できます。関学の問題は基礎的な知識が前提の上で考察する力を問うため、まずはこの参考書で基礎固めをしましょう。章末問題も豊富なのでインプットとアウトプットを同時に進められると思います。 |
| 関西学院大学合格レベル | 生物重要問題集 | 全国の入試頻出問題を体系的に網羅しており、分野ごとの演習量を確保できます。難易度はやや高めですが、関西学院大学の難問にも対応できる力を養えます。受験まで時間の無い方はこの問題集よりも過去問演習を優先してください。 |
| 関西学院大学 赤本 | 関西学院大学特有の、図表や実験データを用いた問題や、設問の切り口を把握する為に過去問演習は重要です。60分内での解答スピードと正確性を鍛えることが合格の鍵となってきます。 |
関西学院大学合格に向けた年間の受験生活
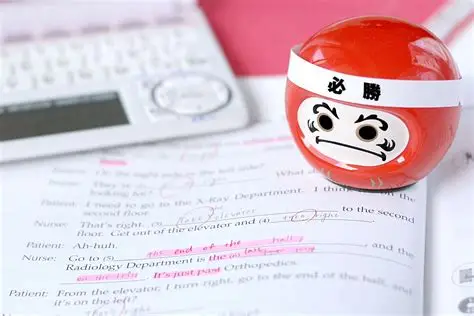
高1まで
【英語】
- 英検準2級〜2級上位レベル
- 高1終了時に中学英語+高校文法の基礎(時制・関係詞・分詞構文・比較・仮定法など)をマスター
- 400〜500語程度の長文を辞書なしで読み切れる読解力を身につける
- 関学は長文読解の比率が高いため、速読力+内容把握力を早期に鍛える
【国語】
(現代文)
- 評論文・随筆・小説など幅広いジャンルの文章に慣れる
- 筆者の主張や要旨をつかみ、選択肢の根拠を本文から探す練習
- 語彙力強化(特に抽象語・評論用語)を意識
(古文)
- 古典文法(助動詞・助詞・敬語)を一通りマスター
- 重要古文単語300語ほどを暗記
- 短い古文を辞書を使ってある程度正確に読み取れる力を養う
(漢文)
- 主要な句形(再読文字・使役・受身・否定)を理解
- 重要語句・漢詩の基礎を押さえる
【数学】
- 数ⅠAを一通り学び終え、基本問題は自力で解ける
- 文系志望:数ⅡBの基礎(数列・ベクトルまで)に触れ、典型問題の解法を身につける
- 理系志望:数ⅡBを進めつつ、数Ⅲの基本公式にも軽く触れる
- 関学は標準〜やや難レベルの典型問題が中心なので、計算精度とスピードを高1から意識
【理科/社会】
- 教科書レベルの流れや基本事項にざっくり触れておく
- 本格的な対策は文理選択が済んだ高2からでも間に合う
- 興味のある分野は先取りしておくと高2以降の理解がスムーズになり有利
- 理科は公式や法則の意味、社会は文化史や地誌の大まかな流れを押さえる
高1から高2まで
【英語】
- 英検2級〜準1級レベル
- 高校英文法を全範囲終了(仮定法・倒置・省略・強調構文などを含む)
- 600〜800語程度の長文を時間内に読み切り、内容一致・要約・推測問題で安定して得点できる
【国語】
(現代文)
- 難度の高い評論文や抽象的テーマにも慣れ、要旨・筆者の立場を的確に把握できる
- 設問形式(空欄補充・言い換え選択・適否判断)のパターンに慣れ、根拠を本文から探せる
- 語彙力・背景知識(哲学・言語論・社会学分野)を意識して増やす
(古文)
- 文法・敬語をほぼ完璧にし、初見の文章でも7〜8割正確に訳せる
- 単語は500語レベルまで強化し、和歌や文学史の基礎も押さえる
- 関学の過去問・同レベル私大の古文問題で実戦演習を開始
(漢文)
- 重要句形を完全習得し、短文ならほぼ辞書なしで読める
- 漢詩の形式や代表的作品・作者を理解
【数学】
- 文系志望:数ⅠAⅡBを全範囲終了し、標準〜やや難レベル問題を時間内に解ける力をつける
- 理系志望:数ⅠAⅡB+数Ⅲの基礎まで一通り終了し、過去問や模試レベルで得点できる計算力を養う
- 関学頻出の典型問題パターン(ベクトル・数列・確率・微積など)を押さえ、反復演習でスピード強化
【理科/社会】
- 文理選択後、本格的に主要科目の入試レベル学習を開始
- 理科(理系):理論〜有機(化学)、力学〜電磁気(物理)、細胞〜遺伝(生物)など主要分野の標準問題を自力で解ける
- 社会(文系):大まかな流れや内容を一通り学び終え、頻出テーマ史・分野別整理を開始
- 資料・統計・実験データの読み取り演習を始め、関学の資料活用型設問に対応できるようにする
高3夏まで
【英語】
- 過去問を年度単位で本格的に解き始め、時間配分と設問傾向に慣れる
- 長文は関学本番レベル(800〜1,000語)を時間内に正確に読み切れる
- 英作文・要約問題が出る学部志望者は、表現ストックを増やし添削を受けて完成度を高める
【国語】
- 現代文:過去問を使って関学特有の選択肢の癖を把握
- 古文:文学史・和歌・古典常識を最終確認し、初見長文でも8〜9割の精度で訳せる
- 漢文:全句形の確認を終え、スピード重視で過去問演習
- 60〜80分の本番形式で、3分野を通しで解く練習を開始
【数学】
- 文系:過去問や同レベル私大の問題を通し演習、時間内完答を目指す
- 理系:標準〜やや難レベルの応用問題に慣れ、過去問で分野別の得点安定化
- 苦手分野を重点的に潰し、ケアレスミスを最小限にする
【理科/社会】
- 過去問で出題傾向を把握し、頻出テーマを重点的に復習
- 理科は計算問題のスピードアップ、社会はテーマ史・統計問題の精度向上
- 弱点分野を夏休み中に集中的に補強
高3秋まで
【英語】
- 過去問を通年分演習し、傾向把握+得点パターンを固定
- 苦手分野(文法、語彙、設問形式別など)を集中的に補強
- 時間短縮のための速読・情報スキャン力を仕上げる
【国語】
- 本番同様の時間配分で過去問演習を繰り返し、安定して合格点を取れる状態に
- 古文・漢文は暗記系(単語・句形・文学史)を完全に仕上げる
- 現代文は選択肢根拠の瞬時判断を磨き、迷いを減らす
【数学】
- 文系・理系ともに、過去問+予想問題で時間配分と解く順番を固定化
- 関学の傾向に沿った大問別の解法パターンを確実に再現できるようにする
- 計算スピードを最終仕上げ
【理科/社会】
- 過去問演習を繰り返し、出題パターンとデータ処理の流れを自動化
- 模試・演習で9割近く取れる分野をさらに伸ばし、弱点分野は最低限合格点を確保できるレベルに
- 時間配分とマークミス防止を徹底
高3冬
高3冬はいよいよ受験直前期です。全体のアドバイスとしては本番当日に迷う要素を減らすため、問題演習・暗記・時間配分を全て固定化しましょう。またこれまでの努力の成果を最大限に発揮するために、生活リズムを試験時間に合わせ、集中力のピークを本番に持っていきましょう。
【英語】
- 過去問・予想問題を本番時間+5分短めで演習し、時間的余裕を作る
- 英語長文は本文構造を瞬時に把握し、設問処理を迷わず行える状態に仕上げる
- 単語・熟語・文法の最終チェックを行い、特に頻出テーマ(文化・教育・科学系)の背景知識も再確認
【国語】
- 現代文は新しい文章に触れつつ、解答根拠を素早く見つける練習
- 古文・漢文は単語・句形・文学史を完璧な暗記状態にし、時間短縮を徹底
- 本番形式で解く練習を週数回行い、国語全体での時間配分を最終調整
【数学】
- 関学の過去問や予想問題を通し演習し、取るべき問題と捨て問の判断を瞬時にできるようにする
- 苦手分野は典型問題だけは必ず解ける状態にする(得点源の確保)
- 本番環境を想定し、1日複数科目を解く形で集中力持続の練習
【理科/社会】
- 直前期用の頻出テーマ・分野別まとめ(自作ノートや市販の最終チェック本)で最終暗記
- 過去問の間違いを全て洗い出し、同じパターンの問題を落とさない状態に
- 本番を意識して時間配分を固定し、マークミス防止の習慣を確立
関西学院大学合格のための参考書ルートを作成しよう

この記事では、関西学院大学に合格するためのおすすめ参考書ルートや、時期ごとの学習到達目標について紹介してきました。もちろん、ここで示したのはあくまで一例であり、現時点での学力や得意・不得意、学習ペースは人によって大きく異なります。
だからこそ、今回の内容を参考に、自分に合った学習プランを自分で組み立ててみてください。
とはいえ、「自分の今のレベルを正確に把握し、何をどの順番で学んでいけばいいのか」を一人で判断するのは簡単ではありません。学習計画づくりや受験指導の経験を持つ専門家に相談することで、現在地と合格までの道筋が明確になり、日々の勉強に迷いがなくなります。結果として、学習効率が高まり、合格にぐっと近づくことができます。
愛大研ハイスクールで関西学院大学合格を目指そう

ここまで読んで、関西学院大学合格に向けた学習の進め方や参考書の選び方が少し具体的になった方も多いと思います。
しかし、頭で理解できても、実際に行動に移す段階でつまずくことは珍しくありません。
例えば、
- 今のやり方で本当に合格まで辿り着けるのか不安
- 模試や演習で結果が安定せず、モチベーションが下がってしまう
- どこから手をつければ効率的なのかわからない
こうした壁に直面すると、独学だけでは限界を感じることもあります。
そんな時こそ、第三者の視点や専門的なアドバイスが大きな力になります。
私が所属する【愛大研ハイスクール 松山市駅前校】では、
現在無料の体験授業や学習相談を実施中です。
あなたの現状を丁寧に分析し、関学合格までの最短ルートを一緒に描きます。
👉校舎紹介記事はこちら:【新ブランド開校】逆転合格専門塾「愛大研ハイスクール」松山市駅前に誕生!
講師は指導歴5年以上のプロ講師or愛媛大学医学部講師です。
全授業が完全なマンツーマン形式で行われ、さらに日々の学習計画や進捗管理まで徹底サポートします。
授業の雰囲気や指導スタイルは、実際に体験してみることで一番実感できます。
「今の勉強法で本当に関学合格まで辿り着けるのか不安…」
「成績は上がってきたけど、まだ合格点まで届く自信がない」
そんな悩みを抱えているなら、まずは一度、面談や体験授業でお話ししましょう。
あなたの現状を丁寧に分析し、関西学院大学合格までの最短ルートをご提案します。
▼体験授業・お問い合わせはこちらから
📞 お電話:089-994-5105
💻 Webフォーム:https://aidaiken.com/trial/
📍 所在地:松山市湊町5丁目(松山市駅から徒歩2分)



コメント