みなさんこんにちは。愛大研ハイスクール編集部です。
- 大阪大学合格のため参考書選びに迷っている
- 今の実力からの阪大合格に向けたレベル別の参考書ルートを知りたい
- 阪大入試まで時間が限られているので、良い参考書を使ってなるべく効率的に勉強したい
今回はそんな悩みを持つ受験生に向けて、大阪大学合格のための参考書ルートを科目別に解説します。
大阪大学の志望学部が決まっている受験生にとっては、共通テスト対策を含めてどの科目から優先的に取り組むべきかも分かるように作成しました。
※本記事は、E判定からの逆転合格がコンセプトの「愛大研ハイスクール」の塾講師が、最新情報をもとに執筆しました。
はじめに|大阪大学合格のために必要なこと

大阪大学は全国でもトップクラスの学力を誇る難関国立大学です。関西圏を中心に非常に人気があり、競争率も高くなっています。
そのため、「どのような仕組みで合否が決まるのか」を正しく理解し、「いつ・何を・どう勉強すればいいか」を明確にしたうえで、確実な学力を積み上げる必要があります。
本記事では、
-
大阪大学の共通テスト・個別試験の配点と仕組み
-
各科目の勉強法(戦略的アプローチ)
-
レベル別参考書ルート(基礎・標準・合格)
を順に解説し、合格を狙える参考書ルートを構築し具体的な学習の道筋を提示します。
大阪大学の入試制度|共通テストと個別試験の配点・特徴
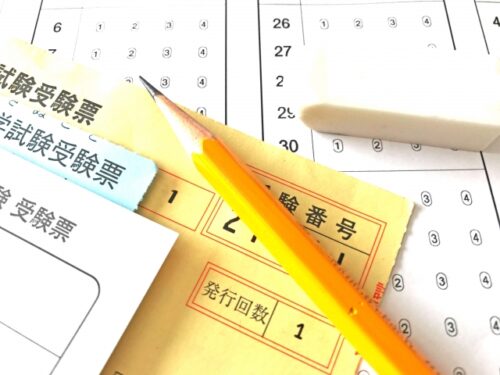
大阪大学の入試では、学部によって共通テストと二次試験(個別試験)の配点比率が異なります。
まずは、その学習計画を立てるために大阪大学の入試形式と科目ごとの配点を確認しましょう。
大阪大学の一般入試は大きく「共通テスト」と「個別試験」の二段階で実施されています。ここでは「共通テスト」と「個別試験(2次試験)」の2つに分けて説明して行きます。
共通テスト
まずは大阪大学の最新版の共通テストの科目別の配点を確認しましょう。
自分の行きたい学部・学科の共通テストの配点をしっかりここで押さえておきましょう。
参照:大阪大学「入試情報」
※前期試験のみ掲載
文学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 260 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 |
人間科学学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学科 | 630 | 100 | 100 | 100 | 200(100) | 100(200) | 30 |
※理科が「基礎」か「基礎を付していないか」で()内の配点となる。
外国語学部(全専攻共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学科 | 235 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 10 |
法学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 40 |
経済学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配点 | 540 | 120 | 120 | 120 | 100 | 50 | 30 |
| B配点 | 60 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| C配点 | 300 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | 15 |
※【全体】A配点は共通テスト540点満点,個別60点満点。B配点は共通テスト60点満点,個別540点満点。C配点は共通テスト300点満点,個別300点満点。A配点で上位65位以内にある者とB配点で上位65位以内にある者を合格者とし,これらを除いた中からC配点で高得点順に合格者を決定する。
理学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 310 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
医学部医学科
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 500 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 |
医学部保健学科
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学専攻 | 625 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 25 |
| 放射線技術科学専攻 検査技術科学専攻 |
520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
歯学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学科 | 470 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 20 |
薬学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 425 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 |
工学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 325 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 25 |
基礎工学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 325 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 25 |
共通テスト配点のポイント
共通テストの元々の配点が1000点であることを考慮すると、大阪大学に合格する上で共通テストの点数はあまり重要ではないように見えます。しかし、多くの学部で個別試験を含めた配点全体のうちおおよそ30~50%程度を占める大事な試験です。
どの学部も共通テストでは75~80%の得点率が必要になってくるので、個別試験だけにとらわれずにしっかりと対策を行う必要があります。
また大阪大学では文系学部でも数学の配点が高くなっていることが特徴です。個別試験でもほとんどの学部学科で数学が科されるので、文系でも数学の対策は万全にしておく必要があります。
個別試験(二次試験)
大阪大学の一般入試では個別試験の比重が大きい傾向があります。
以下に、各学部ごとの個別試験の配点を記します。
※個別試験において科目が選択できるものについては一例を表に示しています。また備考欄にてどの科目から選択できるかを記してあります。
参照:大阪大学「入試情報」
文学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 400 | 150 | (100) | 150 | (100) | – | – |
※数学or地歴公民を選択
人間科学学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学科 | 600 | 200 | 200 | 200 | – | – | – |
外国語学部(全専攻共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学科 | 500 | 100 | (100) | 300 | (100) | – | – |
※数学or地歴公民を選択
法学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 600 | 200 | 200 | 200 | – | – | – |
経済学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配点 | 60 | 20 | 20 | 20 | – | – | – |
| B配点 | 540 | 180 | 180 | 180 | – | – | – |
| C配点 | 300 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
※【全体】A配点は共通テスト540点満点,個別60点満点。B配点は共通テスト60点満点,個別540点満点。C配点は共通テスト300点満点,個別300点満点。A配点で上位65位以内にある者とB配点で上位65位以内にある者を合格者とし,これらを除いた中からC配点で高得点順に合格者を決定する。
理学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 700 | – | 250 | 200 | – | 250 | – |
医学部医学科
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 1500 | – | 500 | 500 | – | 500 | – |
※医学科は個別試験で面接あり
医学部保健学科
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学専攻 | 400 | – | 100 | 200 | – | 100 | – |
| 放射線技術科学専攻 検査技術科学専攻 |
675 | – | 225 | 225 | – | 225 | – |
歯学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学科 | 1200 | – | 300 | 300 | – | 300 | – | 300 |
薬学部
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 小論文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 700 | – | 250 | 150 | – | 250 | – | 50 |
※個別試験で面接あり
工学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 700 | – | 250 | 200 | – | 250 | – |
基礎工学部(全学科共通)
| 学科 | 合計点 | 国語 | 数学 | 外国語 | 地歴公民 | 理科 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 700 | – | 250 | 200 | – | 250 | – |
個別試験(二次試験)配点のポイント
どの学部も個別試験重視であることがわかります。特に数学は文系学部でも科されることがほとんどで、配点も大きいです。
良く言えば共通テストの失敗を二次で取り返す余地がある一方、二次試験でしっかりと得点ができないと厳しい戦いになります。
英語・数学・理科(文系は国語・社会)の記述力がカギとなると言えるでしょう。
個別試験でも共通テストと同様に、配点の大きい科目を安定して得点できるような勉強計画を立てる必要があります。
各科目の勉強法|個別試験( 二次試験)へのアプローチ

ここからは各科目でどのような力をつける必要があり、またどのような勉強法をする必要があるのかを解説していきます。
英語(文理共通)の出題傾向と頻出分野
大阪大学の英語は、典型的な難関国公立大のスタイルを持ちながらも、全体として難易度はかなり高めで、安定して合格点を取るのは簡単ではありません。問題構成には一定のパターンがあり、例年は以下のような形式が多く見られます。
-
大問1:英文和訳(2問)
-
大問2:長文読解問題
-
大問3:自由英作文
-
大問4:和文英訳(※(A)は共通問題、(B)は文学部とそれ以外で問題が分かれる)
特に外国語学部では、他学部と異なる傾向が顕著で、
-
非常に長い長文問題(1500語程度)
-
独自の和文英訳
-
リスニング問題の導入
などが特徴です。他学部以上に高い総合力と対応力が求められます。
長文問題全体の難度も高めで、読解だけでなく速読力も重要です。特に外国語学部では、時間内に情報を正確に処理するスキルが不可欠です。
また、自由英作文が課される点も特徴的で、単に英語を書けるだけでなく、自分の考えを筋道立てて伝える力が求められます。テーマは年度によってさまざまですが、意見を英語で論理的に述べる練習は早いうちからしておくのがおすすめです。
長文読解
-
論理展開が複雑な評論・論説文が多く、自然科学・社会科学・文化など幅広いテーマ
-
1,000語以上の長文も頻出
-
設問形式:内容一致・空所補充・和訳・英訳・要約・自由英作文(多肢選択は少なめ)
和訳・英訳
-
抽象的かつ文構造が複雑な英文が出題される
-
和訳は文脈理解と論理性が問われる
-
英訳では自然な日本語→自然な英語への転換能力が問われる
英作文(特に外国語学部で重要)
-
自由英作文(意見論述型)が頻出
テーマ例:「SNSと現代社会」「大学の役割」「異文化理解」など -
字数制限:80〜150語程度
-
外国語学部では英語での要約・ディスカッション型もあり
要約・文整序・文補充(頻度や学部により変動)
-
指定された段落や全文の要約を英語で書かせる問題
-
論理構造を捉え、簡潔に表現する力が必要
学部別の特徴(例)
| 学部 | 特徴 |
|---|---|
| 文学部・法学部 | 読解中心。高度な論理構造・抽象テーマの評論文+和訳・英訳・簡単な英作文 |
| 経済学部 | 長文読解+和訳・英訳+自由英作文(経済や社会テーマが多い) |
| 外国語学部 | 読解・要約・自由英作文など記述量が圧倒的に多く、英語運用力が問われる |
| 医学部(医学科) | 医学部でよく問われる文構造の複雑な評論文読解・英訳などが出題される |
| 工・理・基礎工 | 長文読解+和訳・英訳中心。文法知識よりも読解力重視 |
数学(文系)の出題傾向と頻出分野
大阪大学の数学は難関国公立大の中でも「標準~やや難」レベルで良問揃いとされ、本質的な理解と計算力、論理的な記述力が問われる試験です。特に二次試験(個別試験)では、見た目の難度よりも思考の深さや答案作成力が差を分ける問題が出されます。
問題数は少なめだが密度は高い
-
大問3〜4題で構成され、1問1問の考察量が多い
-
単純な計算よりも、論理的な記述や構成力が重視される
複数単元の融合問題が多い
-
例えば「数列+関数+場合の数」のように、分野をまたぐ問題も珍しくない
-
教科書の枠を超えた応用力が必要
正確な記述力が差を分ける
-
部分点が多く与えられる試験
-
答えだけでなく、導出過程を論理的に説明できるかが非常に重要
頻出単元(文系数学)
| 分野 | 出題傾向・対策ポイント |
|---|---|
| 数列(数B) | 漸化式の誘導・一般項・和の計算・極限などが頻出 |
| 場合の数・確率(数A) | 場合分けや条件付き確率など。論理的処理と丁寧な記述が必要 |
| ベクトル(数B) | 平面内のベクトルが多く、座標幾何的な視点も必要 |
| 図形と計量(数A) | 余弦定理や三角比を用いた証明問題などが出やすい |
| 関数・グラフ(数I) | 関数の最大・最小、グラフの変化、整数解の個数など |
| 整数問題(数A) | 式変形や場合分け、整数条件の論証問題なども見られる |
| 数学的帰納法 | 数列や不等式での証明問題として出ることあり(近年は減少傾向) |
数学(理系)の出題傾向と頻出分野
理系数学では「典型問題の理解+正確な答案作成力」が必須となると言えるでしょう。
特に難問対策よりも、「標準~やや難」を完答できるかが勝負となります。教科書の徹底理解を問うような問題が多くなっています。時間配分とミスの削減が理系阪大数学の合否を分けると言っても過言ではありません。
標準~やや難の良問中心
-
難問奇問は少なく、正攻法で解けるオーソドックスな問題が中心
-
ただし、誘導に乗り遅れると泥沼にはまる構造の問題が多い
複数分野の融合問題が多い
-
「数列+微積」「ベクトル+複素数」「確率+関数」など
-
教科書内容から飛躍した発想力・変形力が求められる
計算量が多め
-
理系らしく、変形・処理スピードと正確さが勝負を分ける
-
手際よく計算・変形できるかが合否に直結する
頻出単元(理系数学)
| 分野 | 出題傾向とポイント |
|---|---|
| 数列(数B) | 漸化式(特に非線形)+極限、和の処理などが定番 |
| 微分積分(数III) | 極限・最大最小・面積・体積・回転体など、多様な応用が問われる |
| ベクトル(数B) | 空間ベクトル多め。内積・垂直条件・体積との絡み |
| 複素数平面(数III) | 複素数を使った図形問題や変形・回転の処理が頻出 |
| 確率(数A) | 条件付き確率・期待値・反復試行。文章量の多い問題で読解力も試される |
| 関数・グラフ(数I) | 関数の性質を用いた証明や最大最小、定積分の応用が見られる |
| 整数(数A) | 整除性・不定方程式・倍数条件など。記述力と論証力が問われる |
国語の出題傾向と頻出分野
阪大の国語は全体的に「読みの深さ」と「書く力」を総合的に問う問題が多いです。知識問題は少なく、論理的な文章構成・説明力が求められます。特に現代文の難度は高く、きちんとした対策と十分な演習なしで高得点を取るのは困難と言えるでしょう。
とにかく記述量が多いのが特徴と言えるでしょう。
現代文の特徴
-
抽象度が高く、哲学・言語・社会に関する論説文が多い
-
設問形式:理由説明・傍線部の意味説明・段落要約など、すべて記述
-
選択問題がほぼ皆無。すべて自分で「書いて示す」問題
古文の特徴
-
主に中古〜中世の物語・説話・随筆が多い
-
設問内容:語句・文法知識+内容理解+理由説明
-
難語が多く出る年もあるが、基本は文脈からの読解が可能
漢文の特徴
-
訓読・句法の正確な読みと内容の理解+理由の説明が問われる
-
主題例:儒教・道教思想、歴史人物の逸話など
-
書き下し+内容説明・主張要約がよく出る
大問構成(例年)
| 大問 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 現代文 | 評論文(哲学・言語・文化論など)。要約・説明・指摘問題など記述多数 |
| 2 | 古文 | 中古~中世文学。文意把握+文法+内容説明(記述) |
| 3 | 漢文 | 史伝・思想系が多い。訓読・書き下し文+内容説明・理由説明など |
理科の出題傾向と頻出分野
大阪大学の理科(二次試験)は、教科書レベルや標準的な問題の確実な理解を前提としたうえで、応用力や思考力が問われる試験です。計算の正確さだけでなく、その根拠や過程を記述する力、すなわち論述力が非常に重視されます。問題は年ごとにテーマが大きく変わる傾向があり、出題分野の偏りや独自の切り口も多いため、柔軟な対応力が求められます。
特に医学部・理学部・工学部では理科の配点が高く、合否に直結する最重要科目となっています。単に答えを出すだけでなく「どう考えたのか」「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できる力を養うことが、合格への大きな鍵となります。知識の暗記にとどまらず、記述型問題に対応できる訓練を積むことが、他の受験生と差をつけるポイントです。
物理
出題傾向
-
大問3題(力学・電磁気・熱力学・波動など)
-
「基本法則+設定の読み取り+記述」で構成
-
新傾向問題も出るが、典型問題の発展型が中心
頻出分野
| 分野 | ポイント |
|---|---|
| 力学 | エネルギー保存・単振動・衝突・円運動など |
| 電磁気 | コンデンサー・電場・磁場・ローレンツ力など |
| 波動 | 干渉・反射・ドップラー効果・光の波動性など |
| 熱力学 | 気体分子運動論・熱力学第一法則など |
対策
-
『体系物理』『入試標準問題集』で典型パターンを習得
-
記述力を鍛えるには『物理教室』のインプットや過去問演習が有効。余裕があれば『理論物理への道標』にまで取り組めば理論構築は万全だろう
-
図示・式変形・単位の扱いを丁寧に行うこと
化学
出題傾向
-
大問3題構成(理論+無機+有機)
-
計算・記述・構造決定・反応経路すべてが出題範囲
-
問題文が長く、読解力も求められる
頻出分野
| 分野 | ポイント |
|---|---|
| 理論化学 | 酸塩基平衡・電池・電気分解・溶液・化学平衡 |
| 無機化学 | 鉱物・反応性・炎色反応・沈殿など |
| 有機化学 | 官能基の反応、合成経路の推測、構造決定など |
対策
-
『鎌田のDoシリーズ』『重要問題集またはマスター問題集』『新理系の化学』を使って基礎~応用・発展を定着
-
有機は『マスター問題集(有機化学)』+構造決定問題の演習が有効
-
反応機構・グラフ読み取り問題の練習も重要。反応機構に関しては新理系の化学や原点からの化学でわかりやすく学べる。
生物
出題傾向
-
大問3題構成(遺伝・代謝・生態系・動物生理など)
-
実験考察問題が中心で、論述問題の比重が高い
-
グラフ・図表読み取り問題や、仮説検証の論理力が必要
頻出分野
| 分野 | ポイント |
|---|---|
| 遺伝・分子生物学 | DNA、RNA、遺伝子発現・操作系・組換え実験など |
| 生理・代謝 | 呼吸・光合成・ホルモン調節・免疫など |
| 生態・進化 | 個体群動態・遷移・適応・共進化など |
対策
-
『生物の完全習得』『生物標準問題精講』『大森徹の生物』で論述を強化
-
データ読み取り問題を意識して過去問・実験考察型問題を解く
-
「なぜそうなるか」まで言語化して説明する練習が重要
レベル別参考書ルート|基礎→標準→合格レベル
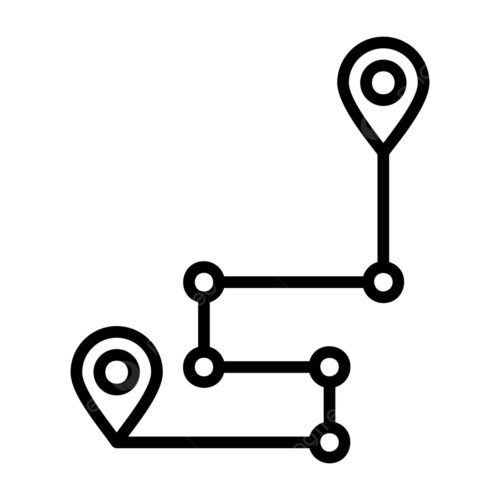
ここでは大阪大学合格に必要なレベル別の参考書ルートを、科目ごとに整理した表で紹介します。
英語の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | ターゲット1900 | 共通・二次に必要な英単語を効率よく習得。英文読解に必要な語彙の基盤固めに有効。 |
| 速読英単語 必修編 | 読解力と語彙力を同時に鍛える。長文の中で語彙を学ぶ形式が阪大に合う。 | |
|
Vision Quest Insight
|
文法の基礎確認から入試レベルまで段階的に対応。文法の穴を埋めるために有用。全問空所補充形式であるため語彙力や作文力も同時に身につく。 | |
| 総合英語 | 文法事項を一通り学べる。例文はそのままフレーズとして暗記すると良い。 | |
| 基礎からの英文解釈クラシック | 精読の基礎である品詞、文型、句と節を初学者にもわかりやすく解説してくれる一冊。 | |
| 標準レベル | 難関大に合格する 英文解釈 Code 70 | 英文解釈の新定番書。構文理解と論理構造の把握を養成。阪大レベルの英文解釈がこの一冊で学べる。 |
| ぐんぐん読める英語長文(ベーシック、スタンダード) | 入試標準レベルの長文演習に最適。長文の読み方や論理展開を学ぶ。 | |
|
Realize 英文「解釈」演習99[発展レベル]
|
英文解釈の総仕上げ。「構文はわかるのに意味が取れない」という人に最適な本。難易度はかなり高いが大阪大学の英語対策なら取り組む価値は大いにある。 | |
| 英作文ハイパートレーニング | 阪大で頻出の英作文の型を学ぶ。短文から自由英作文まで対応。 | |
| 合格レベル | 阪大の英語(過去問25カ年) | 出題傾向や形式の分析、記述の書き方確認に必須。 |
|
大学入試 最難関大への英作文ハイパートレーニング
|
阪大特有の難解な和文英訳対策に最適。ここまで仕上げれば英作文で足を引っ張ることはなくなるだろう |
阪大の英語は難易度が高く、特に記述問題での対策をしっかり行えるルートを作成しました。この参考書ルートに沿って学習していきある程度の知識と力がつけば『大阪大学の赤本』に進むことになります。大阪大学では記述問題が多く出題されるので、解釈系・英作文トレーニングの問題集を多く進めることが重要になります。また記述問題はしっかりと添削を受けることが大切です。
文系数学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 数学I・A入門問題精講 | 基本事項の確認と典型問題の解法習得に適した入門書。 |
| 白チャート(I・A・II・B) | 共通テスト対策にも使える網羅性。解説が詳しく初学者向け。 | |
| 標準レベル | 入試数学解法のセオリー | 思考力を問う標準〜応用問題を豊富に掲載。二次試験対応力を高める。解説が非常に丁寧。 |
|
文系の数学 (重要事項完全習得編)
|
頻出パターンを中心に解法パターンを定着させる。 | |
| 合格レベル | 阪大の数学(文系) | 阪大の過去問演習用。記述対策や答案構成力を鍛える。 |
数学では特に土台となる基礎レベル、標準レベルの演習の質が重要になってきます。
教科書レベルの問題は徹底的に演習を行い、暗記的に解法を覚えるのではなく「なぜそうなるのか」を理解することを意識しましょう。文系は数学ⅡBCまでしっかりと基礎を固めてから標準レベルや個別試験レベルの問題に進むようにしましょう。次のレベルに進んだ時に、理解に不安を感じた場合は基礎レベル・標準レベルに戻って学習することをお勧めします。
理系数学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 入門問題精講(I・A・II・B・III) | 基礎力養成に最適。教科書レベルの入門問題の網羅と丁寧な解説。 |
| 青チャート(I・A・II・B・III) | 定番の参考書。例題→類題構成で理解と演習がしやすい。例題は手が勝手に動くまでやり込むこと | |
| 標準レベル | 数学の真髄(論理・写像) | 大阪大学合格に必要な論証力をつけるのに最適な一冊。全分野の記述力の底上げとなる。 |
| 新数学スタンダード演習 | 入試本番レベルの典型問題を網羅。ここに載っている問題はスラスラ解けるようになるまで徹底的にインプットすること。 | |
| 合格レベル | 阪大の数学(理系) | 阪大の過去問25年分を収録。形式・傾向の分析にも役立つ。 |
文系数学と同様に、土台となる基礎レベル・標準レベルの演習の徹底を意識しましょう。理系は文系と比べて配点も大きいので、1.5〜2倍ほど数学に時間をかけることになる場合が多いです。数学は優先的に、早めに取り組むようにしましょう。理系の場合でも次のレベルに進んだ時に、理解に不安を感じた場合は基礎レベル・標準レベルに戻って学習することをお勧めします。
国語の参考書ルート
現代文
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 田村のやさしく語る現代文 | 現代文の読み方を丁寧に解説。現在文の基礎が分かる。 |
| 入試現代文へのアクセス基本編 | 基本的な読解の現代文の問題の演習を積む。 | |
| 標準レベル | 入試現代文へのアクセス 発展編 キーワード読解 |
内容がより本格的な現代文の問題。 |
| 入試現代文へのアクセス完成編 現代文読解力の開発講座 |
入試に向けて演習の総まとめになる。 | |
| 合格レベル | 阪大の国語(過去問) | 記述型問題の傾向をつかむ。答案作成の練習に活用。 |
| 現代文記述トレーニング | 記述力を磨くための実践問題集。添削例も参考になる。 |
現代文については共通テストの過去問も十分に読解力向上に使うことができます。また、基礎または標準レベルが終わった後に、1年分は阪大の国語を解くようにしましょう。最終的にどのレベルの問題を解くのかを知っておくのかは非常に重要です。
どの教材にも言えることですが、解説を読み込むことが重要です。解説作成者は基本的に優秀な国語読解者です。その思考を追って理解することは、必ずあなたの読解力の形成に役立ちます。逆に解説を読まないことはその教材の魅力を半減させてしまいますので、解説を理解できるまで読みましょう。
物理の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 物理教室 | 教科書レベル〜やや発展の基本事項を網羅。全て覚えこむまで何度も読み返し、常に手元に置いておくと良い。 |
| 体系物理 | 入試の入門〜典型問題を徹底的に網羅している。このレベルが確実に解けるかどうかで合否が分かれるといっても良い。 | |
| 標準レベル |
入試標準問題集[物理基礎・物理]
|
入試問題演習に最適。標準〜難レベルの問題が網羅してある。 |
| 標準問題精講 | 演習の総仕上げ。複雑な設定の問題が多く、難問演習はこの本までで十分。 | |
| 合格レベル | 阪大の物理(過去問) | 実際の出題問題から「傾向」を把握。 時間を測りながら解いていくこと。 |
物理も基礎レベルの重要事項を徹底理解することを大切にしましょう。そこから標準レベルや個別試験レベルの演習に進んだ際に、本番レベル演習の質を高めることにつながります。基礎レベルの参考書をおろそかにしないでください。理解に不安を感じたら基礎レベルに戻ること、公式を丸暗記しないこと、仕組みや理屈を理解することを意識しましょう。
化学の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 鎌田のDOシリーズ(理論・無機・有機) | 基本の暗記事項とその仕組み、最低限の例題で化学の基礎を網羅。 |
| 新理系の化学 | 大学レベルの知識まで踏み込み化学の全分野を解説してあり、軌道や反応機構も学べる。 | |
| 標準レベル | 重要問題集 | 頻出分野を網羅し、典型パターンに強くなる。 |
| マスター問題集 | 標準〜難関大向けの典型問題が中心。解説がかなり丁寧。重要問題集と被る問題も多いため解説の好きな方を選ぶと良い。 | |
| 合格レベル | 阪大の化学(過去問) | 出題傾向の分析や答案作成力の養成に効果的。 |
化学も物理同様、基礎レベルの重要事項を徹底理解することを大切にしましょう。そこから標準レベルや個別試験レベルの演習に進んだ際に、本番レベル演習の質を高めることにつながります。基礎レベルの参考書をおろそかにしないでください。理解に不安を感じたら基礎レベルに戻ること、公式を丸暗記しないこと、仕組みや理屈を理解することを意識しましょう。文字ばかりの解説や参考書だけで理解できない場合には、YouTubeを使うこともお勧めです。
生物の参考書ルート
| レベル | 参考書名 | 参考書の特徴 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 生物基礎問題精講 | 教科書内容の理解と基本問題の演習ができる。 |
| 大森徹の最もわかりやすい生物 | 体系的な解説で、生物の全体像をつかみやすい。 | |
| 標準レベル | 生物の重要問題集 | 典型問題の繰り返しで解法パターンを定着させる。 |
| 生物合格77講 | 論述対策に強く、記述型の出題傾向に対応。 | |
| 合格レベル | 阪大の生物(過去問) | 阪大特有の記述量の多い問題に慣れるために有効。 |
| 生物標準問題精講 | 記述を意識した演習で答案作成力を鍛える。 |
自分のレベルに合った参考書ルートで大阪大学合格を目指そう
大阪大学合格のためには受験勉強を本格的に開始する前に、受験勉強の計画を綿密に練る必要があります。参考書ルートの作成は、「大阪大学合格」という目標を実現するためにすべきことを明確にしてくれます。
これから受験勉強を始めようというあなたは、学習内容が明確にせず闇雲に勉強を進めて行かないようにしましょう。今回ご紹介した参考書ルートを参考に、まずは学習計画を立ててから、受験勉強を始めてください。
すでに受験勉強を始めている受験生も、今あなたが取り組んでいる参考書が自分のレベルに適しているのかそして、闇雲な勉強になっていないかの確認をするために、ぜひ今回ご紹介した参考書ルートを参考にしてみてください。
愛大研ハイスクールでは受験生の参考書に関する無料相談も行っています

今回ご紹介した参考書ルートを使えば、どのレベルの受験生がどんな参考書を利用すれば良いのかというがわかったと思います。
しかし、「実際の参考書の選定」や「学習の管理」については受験生1人での徹底は難しいのが現状です。
愛大研ハイスクールの自習コンサルティング授業では、受験生1人1人に寄り添った学習計画を作成し、それの徹底管理を行っています。
また、完全1対1の個別指導では、受験生1人1人にあったオーダーメイドの授業計画によって受験生の日々の学習をサポートしています。
そんな愛大研ハイスクールでは、無料相談や個別指導を体験できる無料体験授業を実施しています。
ぜひ、受験に関して少しでもお悩みのあなたのお申し込みをお待ちしております!
愛大研ハイスクール紹介記事:【新ブランド開校】逆転合格専門塾「愛大研ハイスクール」松山市駅前に誕生!



コメント