こんにちは。愛大研公式ブログ編集部の茶山です。
今回は、愛媛大学に合格したいなら!【受験のプロが勉強方法と対策を語る】の記事でお伝えしたのに続き、
愛媛大学二次試験(英語)の傾向と対策、そして本番で高得点を取れるための勉強法を、実際に愛媛大学に合格した経験を持つ塾講師の立場と経験から解説していきたいと思います。
まだ上記の記事を読まれていない方は一度読んでいただくことをお勧めします!
また、愛媛大学二次数学についても以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
関連記事→愛媛大学二次試験(数学)の傾向と対策【例題解説もあり】
各学部ごとの入試傾向(英語)

ここからは、入試問題の傾向の傾向について、学部ごとに見ていきましょう。
法文・工学部
まずは、法文学部・工学部の入試問題の傾向について見ていきます。
両学部とも、問題は同じで試験時間は100分となっています。
大問1・2(長文問題)
最初の大問で課される長文問題は、単語数400~800語程度の、中程度の長さとなっています。問題傾向としては、下線部和訳問題と、本文の内容を問う記述問題がほとんど全てを占めています。
英語を記述する問題や、記号問題はほとんどないため、書かれている内容を正確に理解する読解力と、日本語で本文の内容をきちんと説明できる文章力が必要となっています。
長文の難易度としては、共通テストと同じか、少し難しい程度です。記号問題が少なく、記述問題が多いという難しさがありますが、センター試験の長文を正確に読解できる人であれば、あまり動揺することなく解くことができるでしょう。
大問3(和文英作文)
大問3では、日本語を英訳する和文英作文の問題が、3~4問出題されています。難易度は基礎的なレベルであり、あまり難しい構文や文法は要求されません。
社会共創学部
社会共創学部は2021年度から英語の試験はなくなっていて、学科によっては総合問題等の中で英語の問題を課しています。
教育学部
次は、教育学部の入試問題について見ていきます。先ほどの法文・社会共創・工学部と同様、試験時間は100分となっています。
大問1・2(長文問題)
教育学部も、大問1・2で長文読解が課されます。分量としては、500~700語と、中程度となっています。問題傾向としては、法文学部その他と同様、下線部和訳と、日本語の記述や説明が多く求められる問題となっています。
2020年度は1000語程度の問題が1題で、それ以外の年は500〜700程度の問題が2題出されています。
数十文字で記述する必要のある問題もあり、正確な読解力だけではなく、現代文の問題で求められるような文章力も必要です。 難易度としては、法文学部その他の問題よりは少し難しめとなっています。
大問3(自由英作文)
大問3では、自由英作文が課されます。これは、教育学部特有の問題となっています。120~150語程度の英文で、質問に対する自分なりの解答を論述する必要があります。
2019年度には、「将来あなたが教師として教えたい教科について英語で説明せよ」という問題が、
2018年度には「部活動の時間を削減すべきかどうか答えよ」という問題が出されました。英語記述能力だけでなく、論理立てて説明する能力も身に付ける必要がありますね。
医学部
医学部は英語の試験を廃止していて、総合問題で英語を取り扱っています。
しかし、傾向自体は変わっていません。現代文の試験問題と英語の長文問題をハイブリッドさせたような問題になっています。ただ文章を読むのではなく、内容を理解し長い文章の全体像を見る力が必要になります。それに加え、日本語での設問に対しての論理的なアプローチができるかが、鍵になってきます。
過去問解説

ここでは各学部ごとに一部の問題を抜粋して、過去問解説を行います。一部の問題のみとはなりますが、あなたの受験勉強に役立ててもらえると嬉しいです!
また、解答はあくまで解答例となります。別解や別の表現を用いることも可能な場合も多いので、必ず自分でも解いてみて添削を受けることが重要です!
法文学部・工学部
Ⅲ. ある母親とその息子の会話である。下線部1,2を英訳せよ。(会話文)
息子:₁明日は朝早く学校に行かきゃいけないんだ。
母親:あら、どうしてなの?
息子:友人と教室で勉強する約束をしたんだ。
母親:まあ、珍しいわね。じゃあ、₂電車に乗り遅れないように早く起きてちょうだいね。
【解答】
1.I have to go to school early tomorrow morning.
(解説)
これはかなり簡単な英作文で、中学英語レベルです。1問目はそのような問題もよく出題されるので落とさないよう気を付けましょう。日本語は主語が欠落していることがあるので、何が主語なのかをしっかり把握する必要があります。今回の使う表現としては、
- ~しなければならない:have to do
- 明日の朝早く:early tomorrow morning
などが使えていれば問題なく書くことができるでしょう。
【解答】
2.Please get up early so that you do not miss the train.
(解説)
この問題も特別難しくはなく、使う表現が分かれば難なく解ける問題です。使う表現としては、
- ~ように:so that ~
- 電車に乗り遅れる:miss the train
この2つの表現を知っていれば、書くことができるでしょう。
Ⅳ.次の文章中の下線部1~3を英訳しなさい。
₁科学研究の第一要件は知識を創出することにある。特に、自然を相手にする科学においては、物質の構造・運動・反応性・質的変化・他との関係性・歴史性などを追究し、そこから得られる原理や法則に関して新しい発見がなくてはならない。 (中略)
このように科学の成果は階層構造をなしており、発見の大小の差はあっても1つ1つがピラミッドの一角を構成している。₂そのいずれもが、人間が獲得した自然に関する新しい知識なのである(むろん、失敗例にも価値がある。それによって再び同じ失敗を繰り返さないからだ)。
₃科学の研究の発端は、科学者個人の好奇心に基づいている。「なぜそうあるのか」を問い質そうとする心の働きである。
(池内了「科学・技術と現代社会」より抜粋)
【解答】
- The first requirement of scientific research is to create knowledge.
- All of them are the new knowledge about nature that humans have acquired.
- The genesis of scientific research is based on the curiosity of (individual) scientists.
(解説)
1.
- 科学研究:scientific research/study
- 要件:requirement
上記の単語とto-不定詞の名詞的用法を用います。requirementが出てこない場合は「重要な事物」に変換し、important matterとしてもよいでしょう。
2.
基本的な単語を用いて、「人間が獲得した自然に関する新しい知識」の部分を関係代名詞や過去分詞を用いた後置修飾で表現します。過去分詞を使うのであれば、
the new knowledge about future acquired by humans となります。
3.
- 発端:origin/start/genesis
- ~に基づいて:be based on ~
- 好奇心:curiosity
- 個人:individual
発端という単語をどう変換するかがこの問題のカギになってきます。genesisという単語を知っている受験生は多くはないと思うので、同じような意味の単語を使って書いてみましょう。
教育学部
Ⅲ.あなたは中学校の英語の教師として教壇に立っています。ある日一人の生徒が、「先生、自分は英語が大の苦手で嫌いな科目の一つです。なぜ自分たちは英語を学ぶ必要があるのですか?」と聞かれました。その生徒の質問に答えるために、あなたの考える英語を学ぶ理由や英語を学ぶことで得られる恩恵を述べなさい。120~150語の英語で書くこと。
【解答】
I think that learning English may be an opportunity to inspire students’ intellectual curiosity, and enables them to improve their communication skills and know the culture of another country. First, motivation to study comes from intellectual curiosity. We cannot predict when intellectual curiosity is inspired, but someone may feel it someday if everyone studies English. Second, in English class, students must talk with other students or teacher in English. They can improve their communication skills naturally. Moreover, some students make new friends through the class of English. Third, students can know foreign culture. Regardless of the country where English is spoken, it is important to give opportunities to know the other countries. Globalization is widespread, so students need to be more interested in foreign countries. Finally, English enables us to experience many things, it will become valuable in our life. (140)
(解説)
自由英作文では、理由を羅列して書く場合には「初めに」、「2つ目に」というような目印のための接続詞を入れるとよいです。
比較したり、ある意見に賛成か反対かを書いたりする場合には、そのほかの接続詞を使うとよいでしょう。特に逆説、順接の接続詞を適宜使うことで、ある主張の強調、論理性を支えてくれるものになり、説得力がある文章になります。また、自由英作文は自分が知っている表現を使って書くことが鉄則です。そのために、自分が言いたいことを数パターンに言い換える練習が必要になります。何回も練習し、型にはめて書いていけばおのずとすっきりとしたわかりやすい文章を書くことができるようになります。テーマに傾向がある場合は、その専門用語や使えそうな単語をあらかじめリストアップし、文章の中で使えるようになっておくと有利になると思います。
問題毎の対策
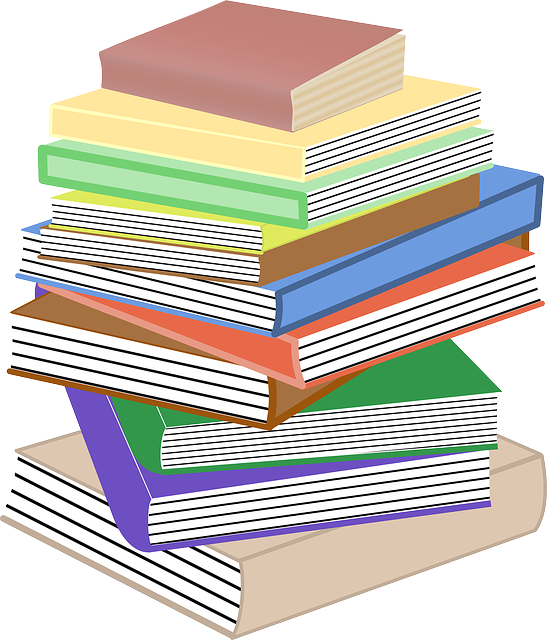
次は、問題の種類に応じて、
- 長文問題
- 和文英作文
- 自由英作文
の3つに分けて解説していきます。
長文問題
長文問題は、先程も見た通り、全ての学部で出題され、比重も一番高いものとなっています。どの学部でも、日本語での説明を必要とされているので、まず解く上で大切になってくるのは、最初に質問に目を通し、何を問われているのか明確にしてから本文を読み進めることです!
それによって、闇雲に文章を読んでいくよりも、どの部分に特に注目するべきかという方向性を定めながら問題を解くことができるので、正確に解答できる可能性が高まります。また、解答の根拠、ヒントになりそうな文章や単語には印を付けながら読むことで、要点を押さえた解答を作ることが出来ますよ。
そして、長文中の下線部和訳の問題では、正確な和訳ができるように、主語と動詞が何かを明らかにした上で解答することが大切です。下線部和訳に関しては、単語と文法を出来るだけ多く覚える、ということが最大の対策となりますので、過去問を解いて、出てくる問題のレベルを把握したら、文法書などでひたすら文法を覚えましょう。
和文英作文
法文学部、工学部の大問3で出題される和文英作文の対策について解説します。まず、和文英作文で心に留めておくべきことは、満点の英文の作成は目指さなくても良いということです。
よほど基本的な問題でない限りは、同じ問題でも使う単語や文法は人によって異なります。自分の持っている文法知識を駆使した上で、出来るだけ日本語のニュアンスを変えることなく、減点を防ぐことを心掛けて解答するようにしましょうね。
ここで、減点を防ぐというのは、時制の一致、スペル、動詞の時制などを特に意識するということです。基本的なミスを重ねてしまうと、それも減点となり非常に勿体ないので、自分の書いた英文を何度も見直すことを徹底しましょう!
自由英作文
教育学部で出題される自由英作文では、和文英作文とは異なり、英作文の能力だけではなく、論理的な文章を組み立てることも必要となります。いきなり英文を書き始めるのではなく、どのような論理展開で、どのような立場に立って書くのかということをある程度考えてから記述を始めるようにしましょう。
和文英作文と同様、余計な減点を防ぐために、時制やスペルなどの見直しも確実に行うようにしてください!
また、単語や文法はもちろん、自由英作文を書くために確実に身に付けたい知識として、接続詞、接続副詞があります。論理的な文章を書くためには、前後の文章を自然に繋ぐ接続語が不可欠です。ただひたすらに思いついた文章を書くだけでは、説得力がなく幼稚な印象の文章となってしまいます。
接続詞として、so(だから)、because(なぜなら)、接続副詞として、therefore(それゆえに)、however(しかしながら)などが挙げられます。しかし、soやbecauseなどの接続詞と、thereforeやhoweverなどの接続副詞では用法が異なりますので、演習を重ねながら正しい使い方を身に付けるようにしましょう。
高得点を取るための勉強法
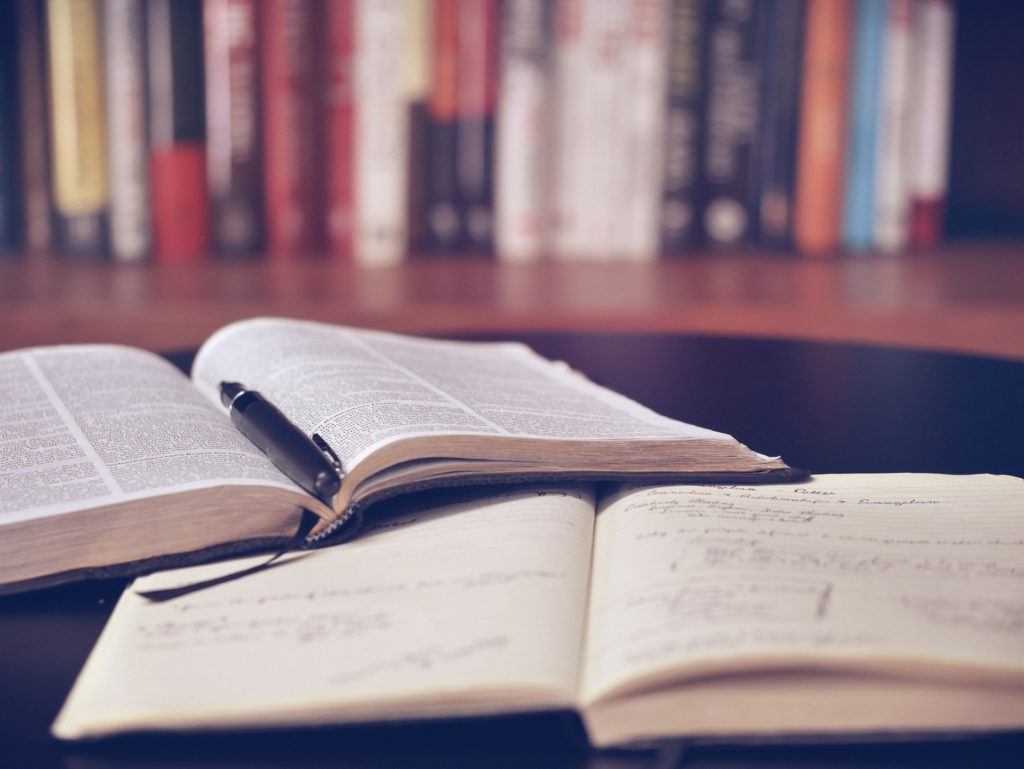
ここからは、高得点を取るための勉強法について、
- 単語
- 文法と構文
- 長文演習
- 過去問演習
の4つの項目に分けて解説していきます。
1 単語
長文の内容を理解したり、英作文を作ったりする時に最も重要なのは、単語力です。そのため、基礎的な単語力の定着は、英語の得点を伸ばすために、高校1年生から徹底するべき事項です。愛媛大学二次試験において身に付けておくべき単語は、基礎的なレベルの単語帳一冊分(目安としては、1500語程度)です。
ここで、効率の良い単語の覚え方を紹介しておきます。まずは、多くの人が実践しているであろう、単語帳を繰り返し見ることで単語を暗記する方法について紹介します。
私がお勧めしたいのは、ただ漠然と単語を眺めるのではなく、日本語訳を赤シートで隠しながら、英単語を見ただけですぐに日本語訳が出てくる状態まで定着できたら次のページへ進むという方法です。
もちろん、時間が経つと忘れてしまうと思いますので、少し期間を空けた後、もう一度同じ方法で復習を行い、単語のインプットとアウトプットを繰り返すようにしましょう。それだけではなく、例文の中でその単語がどのような形で使われているのかを確認しながら覚えることで、その単語が、自分のものとして使えるものとなっていきます。
また、単語帳を単なる暗記ツールとして使うのではなく、長文中に出てきた単語で分からない単語があれば、それを単語帳で参照してチェックする、という使い方も有効です。いわば、単語帳を辞書のように使う方法です。そうすることで、色々な形で単語に触れることができ、定着度アップにつながります。
2 文法と構文
文法問題は、愛媛大学二次試験の中では出てくる機会は少なく、直接的には点数に結びつかないと考える方もいるかもしれませんが、英作文、特に和文英作文を作る際には、「この文法や構文を知らないと解けない」というような状況に多く遭遇します。和文英作文、自由英作文問わず、英作文を課されている学部では、基礎的な文法や構文の知識は必須です。
マークシート問題とは違い、「知っているだけ」「訳せるだけ」の文法知識では、二次試験においてはあまり役に立ちません。しかし、いきなり実用レベルまでもっていくのは厳しいと思いますので、まずは自分が持っている文法書を何周もして、まずは様々な文法を知識として身に付ける段階から入るのがよいでしょう。
人によって個人差はあると思いますが、文法を駆使できるレベルにまで達するためには、最低でも15~20周は文法書を見る必要があります。文法書の中に書かれている例文だけではなく、色々な文法知識や単語を組み合わせて自分なりに英文を作る、という方法がベストです。それにより、単語力、文法力だけでなく、二次試験の点数に直結する文章力を身に付けることができます。
3 長文演習
ここからは、長文演習について説明します。
まず念頭に置いてほしいことは、単語力や文法知識が不十分な状態で長文演習を重ねても、あまり意味がないということです。そのような状態で長文を解いてしまうと、分からない部分が多すぎて、一度の長文で覚えるべきことがあまりに多くなってしまいます。
そうなると、結局、あまり理解が及ばないまま、その演習を終わってしまう、ということにつながってしまうため、優先すべきは、先述した単語や文法知識を身に付けることです。
だからといって、2年生までは100%全て基礎知識の勉強に費やし、3年生からは100%全て長文演習に特化して勉強する、というような勉強を推奨しているわけではありません。というのも、基礎的な知識の理解は長文演習と並立して行うことで、効率よく行うことができる上に、少しずつ長文に慣れておかないと、文章全体を体系的に理解する読解力は中々身につかないからです。
スポーツなどの世界でも、最初は素振りをしたり基礎体力をつけたりすることを重視して、基本的な能力が身についたら、それと並行して、徐々に実践的な練習を増やしていきます。それと同じことが、英語の勉強にも言えるのです。
自分の現在の能力と相談しながら、自分が今どのような演習を重視するべきなのか、ということを考えながら学習を進めましょう。
4 過去問演習
問題の傾向を掴み、自分が今どのくらい点数をとることができるのか、ということを理解するためにも過去問演習は大切です。過去問を解く時期については、一度、3年生の秋頃に解くことをお勧めします。
それを通して、自分のある程度の実力を理解し、どのような勉強を進めるべきかが分かります。ただ、過去問を多く解いて演習を重ねるのは、大学入学共通テストの後にした方がいいでしょう。
また、過去問演習において重要なのが、先生に答案の添削をしてもらうことです。特に英作文については、先生のアドバイスを聞くことで、英作文を作る能力を磨くことができます。
また、時間をきちんと計って解くことも意識しましょう。自分がどのような順番で解くのが一番良いのかということが、時間を計りながら解くことで見えてきます。
英語を得点源にして、愛媛大学合格を目指そう
いかがでしたか?
自分が目指したい学部の問題分析をしっかりと行った上で、自分の今の実力と照らし合わせながら自分が行うべき勉強を効率よく行うことが大切です。
また、志望校合格には正確な目標設定と綿密な計画が必要です。
私たち愛大研はあなただけの志望校合格までの計画を立案することができます。
本記事で紹介した傾向や対策、勉強法が、英語の点数アップと、志望校合格に役立つ事を祈っています。
愛大研ブログでは愛媛大学の各学部ごとの詳細な入試対策の解説も行っています。
是非ご活用ください!
愛大研では無料体験授業を行っています
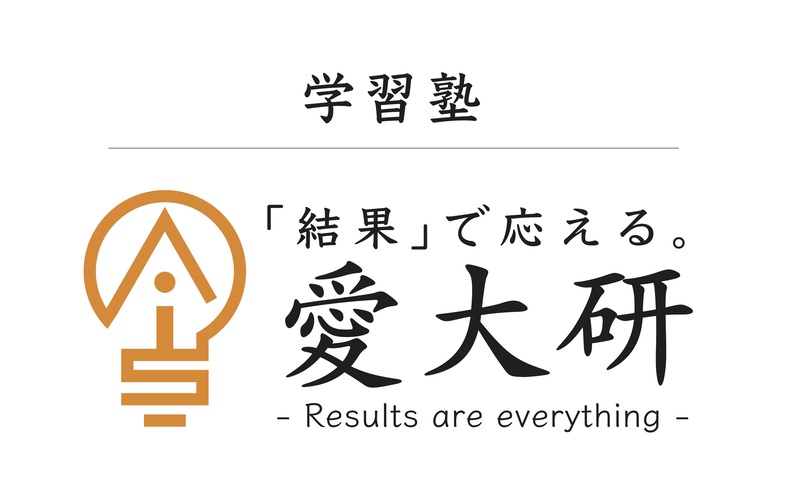
本記事で、愛大研に少しでも興味を持った方や、大学受験に向けての学習計画をどのように作ったらよいのか不安…という方に向けて、
愛大研では、講師と生徒か完全1対1で授業をする個別指導に加え、講師が生徒の状況を見ながら、志望校などと照らし合わせ具体的な勉強スケジュールを提示する自習コンサルティングも行っています。
愛大研紹介記事→E判定からの逆転合格を生み出す松山市の学習塾『愛大研』の無料体験授業とは?
もちろん、愛大二次英語も対策可能です。
現在、無料体験授業も随受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
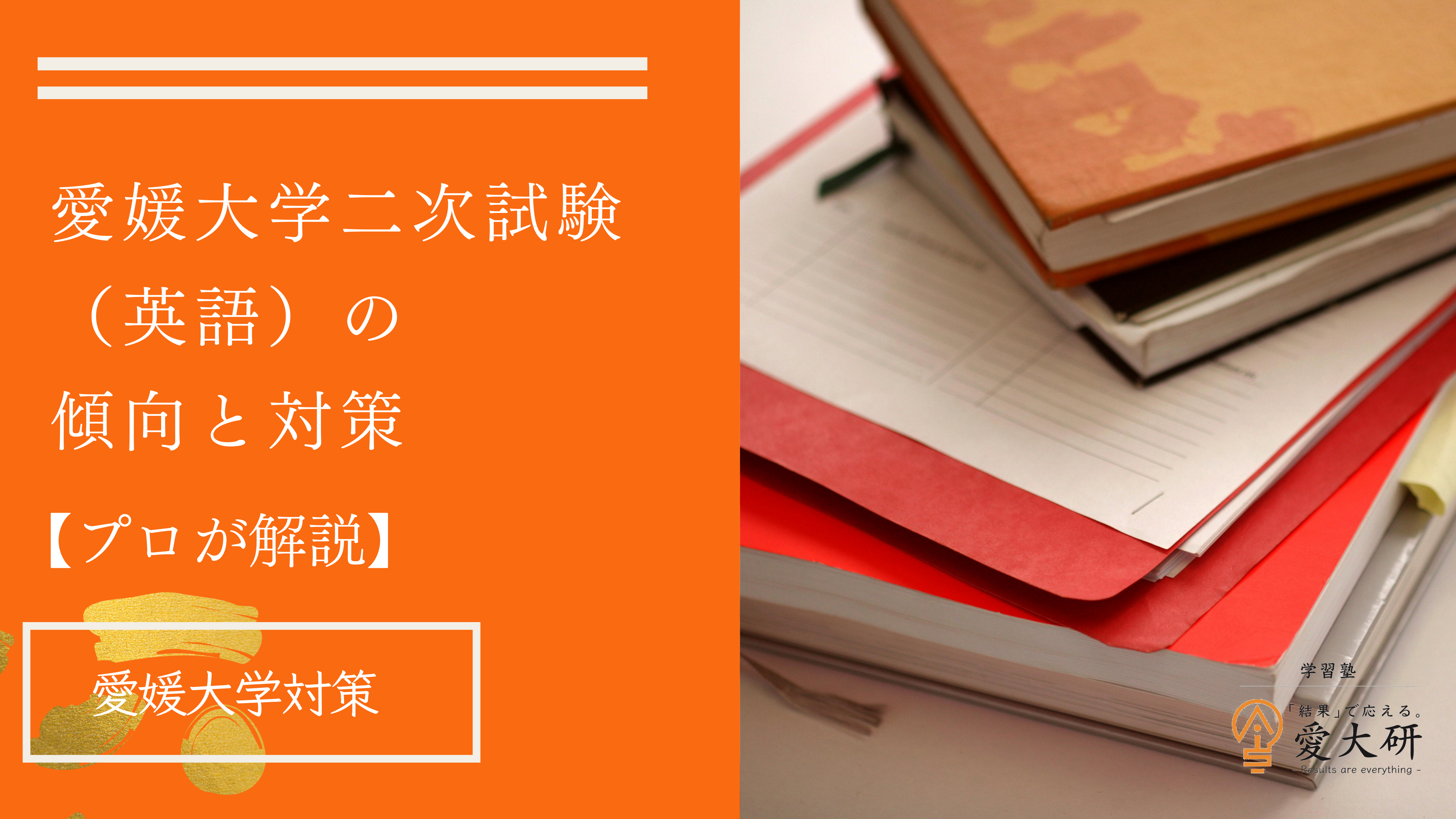
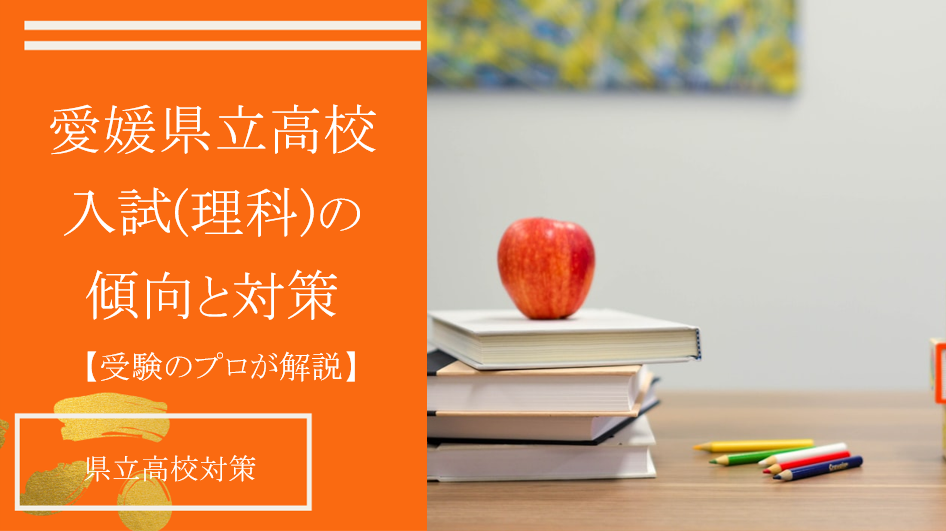

コメント