こんにちは、愛大研編集部の武智です。
この記事を見てくれたあなたは、
「総合型選抜の対策がしたい!」
「グループディスカッションってなに!?」
このように思っているかもしれません。
グループディスカッションを出題される学科は多くなく、
あまり聞きなじみもない方がほとんどではないでしょうか。
今回はそのような方に向けて、大学入試におけるグループディスカッションの傾向と対策について、私が普段指導することの多い愛媛大学社会共創学部の受験を例に挙げながらに焦点を当ててご紹介します。
関連記事
学校推薦型/総合型選抜で愛媛大学を目指すなら!
総合問題を攻略するには!【総合型選抜Ⅰ】
愛媛新聞取材記事
→【変わる大学受験】推薦入試で合格するには 松山市の学習塾が愛媛大学を徹底分析
グループディスカッションとは

グループディスカッションとは、集団での話し合い(討論)のことです。
試験では4~8人ほどのグループに分かれ、
試験官から与えられたテーマに沿って話し合いを進めます。
グループディスカッションと一括りに言っても、いくつか種類があります。大学入試においてよく出題されるのは下記の3つです。
- 自由討論型
- 課題解決型
- ディベート型
例えば愛媛大学社会共創学部では、どちらかというと課題解決型のテーマが多いです。
過去に出題されたテーマ例を2つ挙げてみます。
- 四国に新幹線は必要かどうか
- キャッシュレスの課題と解決策は何が考えられるか
課題解決型はある課題について分析し、解決に向けて議論していくのが特徴ですね。
愛媛大学でグループディスカッションを課している学部
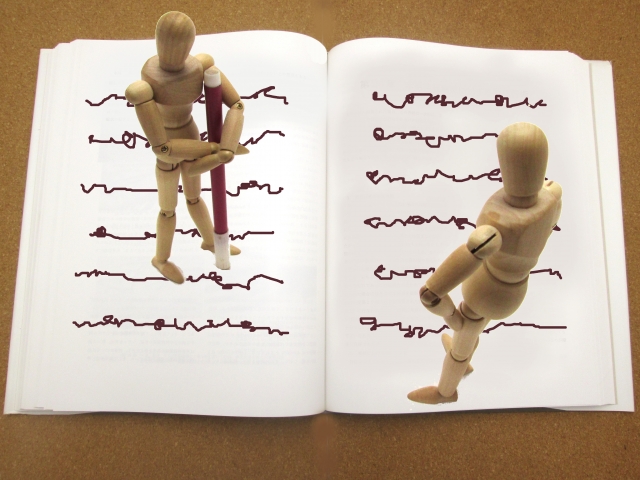
そもそも、どのような大学・学部・入試形態でグループディスカッションを採用しているのでしょうか。
今回は愛媛大学を例に挙げてグループディスカッションを課している学部と学科はどのくらいあるのかを見ていきましょう。
社会共創学部
・全学科の総合型選抜Ⅰ
教育学部
・全課程の総合型選抜Ⅱ(中等教育コース美術教育専攻と特別支援教育コースを除く)、一般入試前期日程(特別支援教育コースを除く)
・初等教育コース小学校サブコースの学校推薦型Ⅱ
愛媛大学では社会共創学部、教育学部がグループディスカッションを実施していることが分かりました。
また、推薦型選抜や総合型選抜に限らず、一般入試の個別試験でも実施する学部があることも分かります。
グループディスカッションの対策方法は?

ここまで、グループディスカッションの全容についてご紹介してきました。
では、実際の入試に向けてどのように対策していけばよいのでしょうか。
時系列順に確認してみましょう。
高校3年生の7月まで
自分の興味のある分野について調べたり、志望学科に関連するイベントに参加したりと、積極的に知見を得るように活動しましょう。
例えば社会共創学部では、地域活性化がテーマに出題されることが多いです。(グループディスカッションに限りませんが。)
個人的には、進路実現や志望学部に直接的に通じる分野を中心に知識を深めると良いでしょう。
また、推薦型/総合型選抜Ⅰの方は、
共通テスト前に面接やグループディスカッション対策に時間を割くことになるので、
今の内から計画的に一般入試対策の勉強も進めましょう。
Ⅰ型入試本番前の3ヶ月はほとんど勉強する時間が無いと思った方が良いです。
一般入試対策に余裕をもって取り組めていると、グループディスカッションの練習に割ける時間も多くなりますよ。
高校3年生8月~10月
トータルで何回練習するか計画を立てましょう。
グループディスカッションは1人で対策できることが少なく、複数人で練習することが望ましいので、早めに日程を決めておくことをお勧めします。
通っている高校によって、学校でできる練習回数は大きく異なります。
20回以上練習する高校もあれば、2~3回しか練習の機会がとれない場合もあります。
早めに学校の先生に確認して、スケジュールを立てておきましょう。
個人的な考えですが、目安として10回は練習しておくといいです。
学校で十分な練習の機会が確保できない場合は、塾や予備校で対策してもらうのも一つの手ですね。
愛大研の愛媛大推薦入試突破クラスによる対策
ここまで、グループディスカッションのテーマや形式、対策の流れなどについてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。
この記事は私がAOⅠ型入試(現 総合型選抜Ⅰ)で社会共創学部に合格した経験も元にしているので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
筆者の出身校では、多くの先生方が推薦入試やAO入試(現総合型選抜)の対策を手厚く行って下さったため、自信を持って入試本番を迎えることができました。
ところが、大学入学後に他校出身の友人や塾の生徒に話を聞くと、「卒業生に前例がないので不安」という声が多かったり、試験対策の内容に大きな差があったりすることを知りました。
そこで私が知っている推薦/総合型入試の対策方法やAO入試合格経験を元に、
これまで十分に試験対策ができなかった生徒に向けたサポートを行いたいと思いました。
愛大研では2021年度から愛媛大推薦入試突破クラスを開講しています。
コンサルティング形式での定期面談や、総合問題対策、グループディスカッション対策などの実践的な対策も行っていますので、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。
オンライン授業も対応していますので、松山市外からのご受講も可能です。(毎年3名ほどが推薦入試突破クラスを受講してくれています)
※定員に達し次第募集を締め切らせていただきます。
愛媛新聞取材記事
→【変わる大学受験】推薦入試で合格するには 松山市の学習塾が愛媛大学を徹底分析
愛大研では無料体験授業を行なっています

本記事で、愛大研に少しでも興味を持ってくださった方や、
「逆転合格で第一志望合格を狙いたい!」という方は、まずは気軽に無料体験授業にお越しください!
愛大研紹介記事→E判定からの逆転合格を生み出す松山市の学習塾『愛大研』の無料体験授業とは?
ともにあなただけの志望校合格のプランを立てませんか?
お待ちしています。
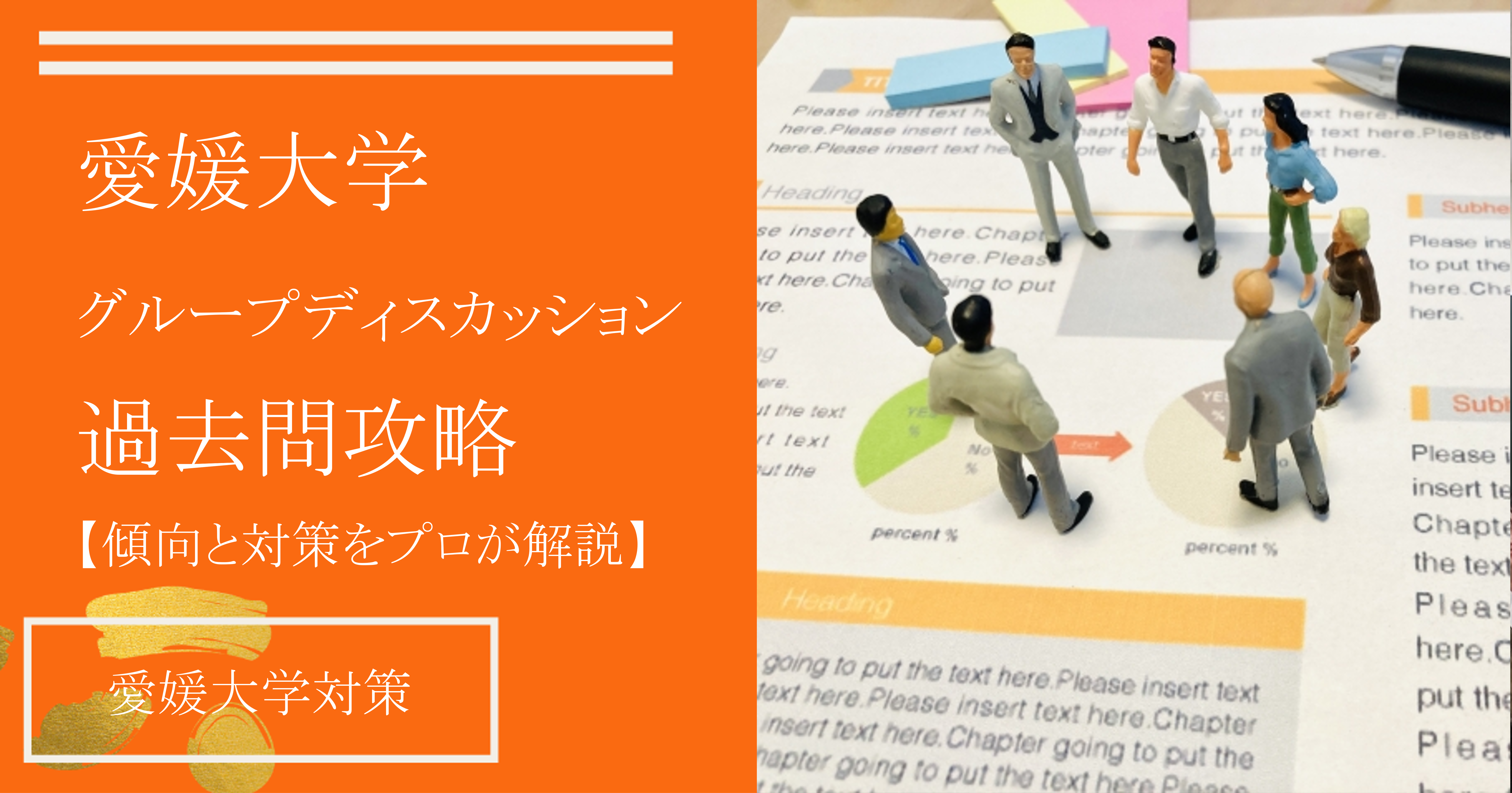
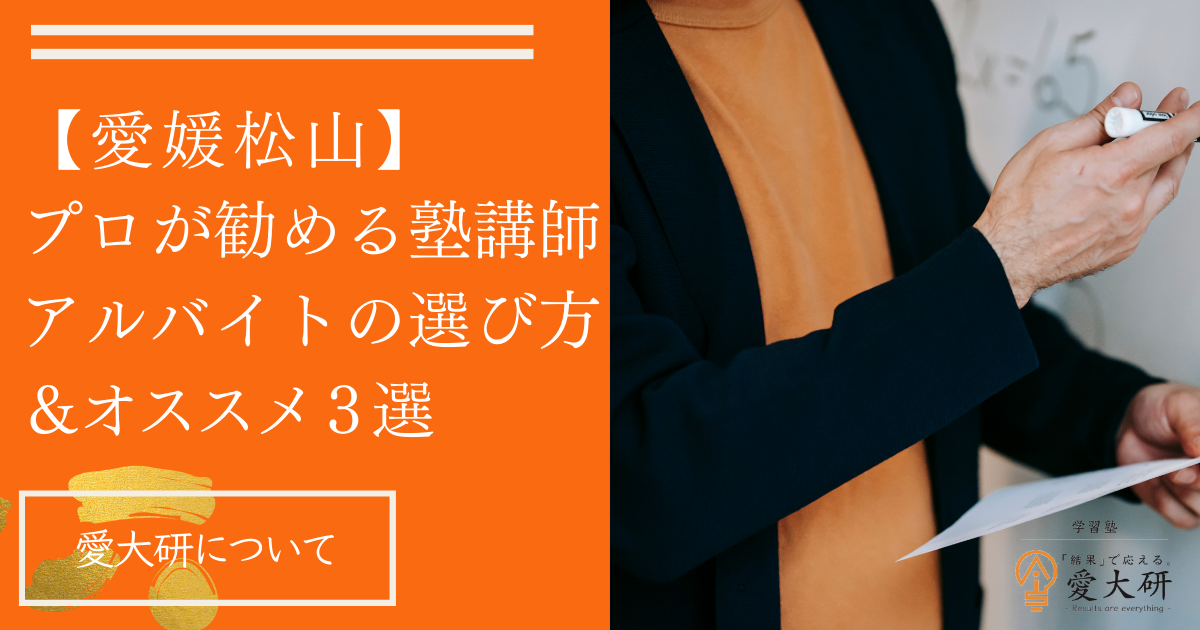
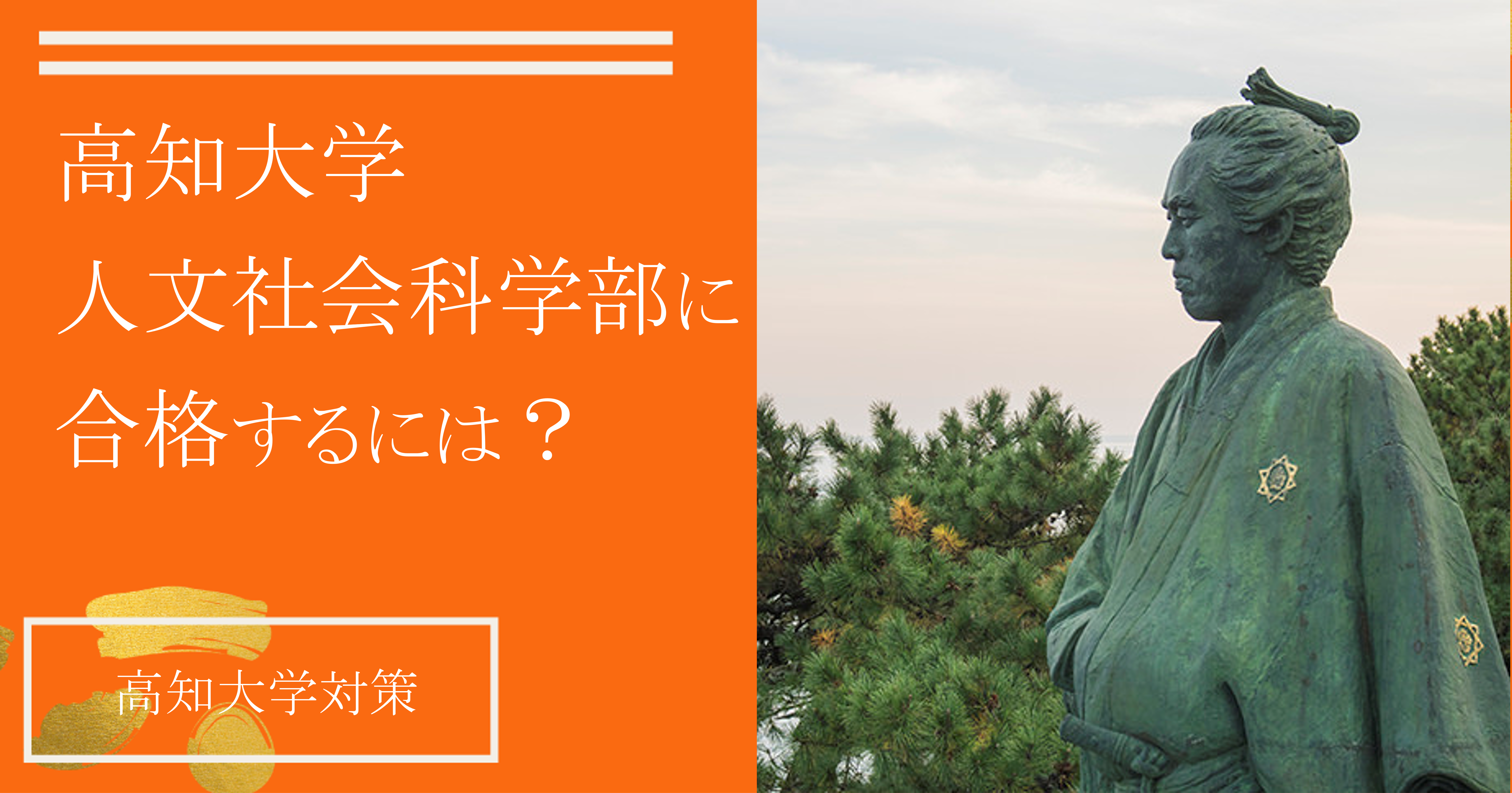
コメント